反社やクレーマー等に不当な行為を要求された場合の法的対応について
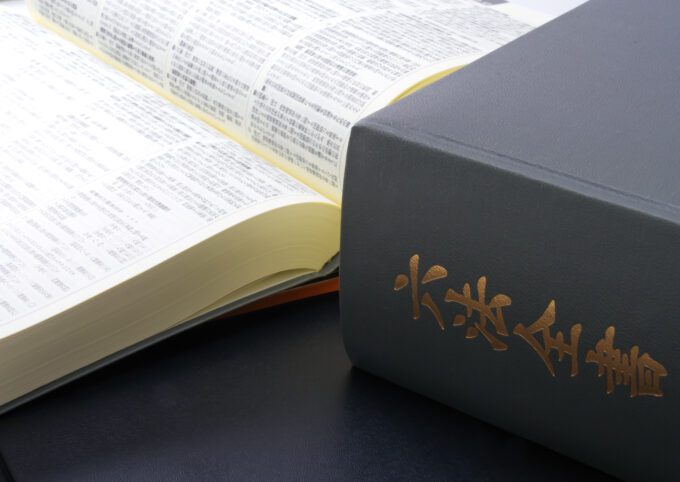
不当な行為を要求する者は、要求に応じてしまった相手からは取れる分を取るだけ取り、断固拒否など毅然と対応する相手に対しては、弱みを粗探しして責め立てたりと、あらゆる手段を講じて金銭を搾取しようとしますが、それも最初だけで、毅然とした対応をし続けていれば退いていきます。
不当な要求はいつ、誰にされるかわかりません。どう対応したらよいか、事前に把握しておくことで、企業であっても、個人であっても、落ち着いて対応することができます。
今回は、不当要求行為がされた場合の対応(法的対応を含む)について簡単にご紹介したいと思います。
不当要求行為とは
どのような行為が不当要求行為であるのか、その明確な定義や基準はありません。
しかしながら一般的に、不当要求とは、法的根拠や社会的妥当性を欠く要求をいうとされています。ただ、行為態様によっては単なるクレームという場合も十分あり得ますし、一般の方ではその判断は難しいといえます。
とはいえ、「不当」であるので、基本的には要求されている内容と、要求する手段がそれぞれ正当か不当かで判断しやすくなるでしょう。
例えば、
- 店員に対する土下座の要求
- 理由のない金銭の要求など法律上義務のない行為の要求
- 「誠意をみせろ」など抽象的な要求
- 暴力を振るって許認可を出させる
- 要求を受け入れないのであれば、何するかわからないぞなどと脅す
- 誹謗中傷などの人格攻撃
- 反社会的勢力とのつながりを示唆する
上記1~3は、不当な要求内容の例であり、4~7は不当な要求手段の例です。
つまり、不当要求とは、要求の内容が不適当又は不相当であったり、要求の態様(手段)が不適当又は不相当な行為といえるでしょう。
不当要求行為への対応
不当要求行為は、まず当事者間で行われるのが通常です。
不当要求行為被害に遭った際のポイントは以下の2つです。
- 絶対に安易に応じないこと
- 必ず複数人で対応すること
安易に応じないこと
不当要求行為がされた場合、相手に威圧され、「怖いしこれで済むのなら・・」と要求に応じてしまうことがあります。
しかし、安易に不当な要求に応じてしまうと、さらにエスカレートする場合も多く、新たな不当要求行為を招くおそれもあります。企業であれば社会的責任や風評被害の点からも避けるべきですし、個人であれば精神的に疲弊してしまうこともあります。
そのため、不当要求行為に対してはまず安易に応じない毅然とした対応をとることが重要です。
そもそも要求に応じる必要があるのか、要求に応じるにしてもどの範囲で応じる必要があるのか、などについては、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
恐怖のあまりご自身で毅然とした対応を取れない場合には、すぐに警察や弁護士に相談してください。
複数人で対応すること
不当要求行為に対して、1人で対応することは絶対に避けるべきです。
不当要求する者は、相手の弱い部分をついて攻撃してきますので、1人ではどうしても限界がきます。
企業であれば、社内での連携や情報共有、場合によっては従業員の安全確保の措置が必要となることもあるでしょう。
個人であれば、すぐに警察や弁護士に相談することです。
不当要求行為への法的対応
通知書等の発送
弁護士がこの種の事案で依頼を受けた場合、不当要求行為者に対し、これ以上不当要求行為をしないよう警告する旨の内容証明郵便を送付します。
その際には、まずは依頼人と相手方を切り離す必要があるので、弁護士受任後の連絡窓口を弁護士のみとし、本人同士での連絡や接触は一切行わせないようにします。
刑事事件化する
不当要求行為が極めて悪質なものであって、犯罪にあたるような場合は、内容証明郵便と併せて、警察とも事前に情報を共有し、連携することもあります。
その場合でなくても、内容証明郵便を送付後も不当要求行為が継続している場合は、警察に対し、被害届の提出や刑事告訴をすることもあります。
仮処分の申立てや損害賠償請求などをすることも
ケースとしてあまり多くはありませんが、民事上の対応をすることもあります。
例えば、面談強要の禁止や架電禁止を求める仮処分の申立て、不当要求行為によって損害が発生している場合は損害賠償請求も検討します。
不当要求行為に対して対応に困ったら弁護士に相談を
不当要求行為は、早期に弁護士や警察に相談することが重要です。
どのような対応をするべきかについては、1人又は企業で考えてもそれが正しいのか客観的には判断が難しいものです。
しかし、弁護士や警察に相談し、連携することで、適切な対応をとることができ、また必要に応じて法的対応をとります。
不当要求行為でお困りの方はお早めに弁護士に相談することをお勧めします。