遺産分割の付随問題~相続財産の中に、共有持分があるとき
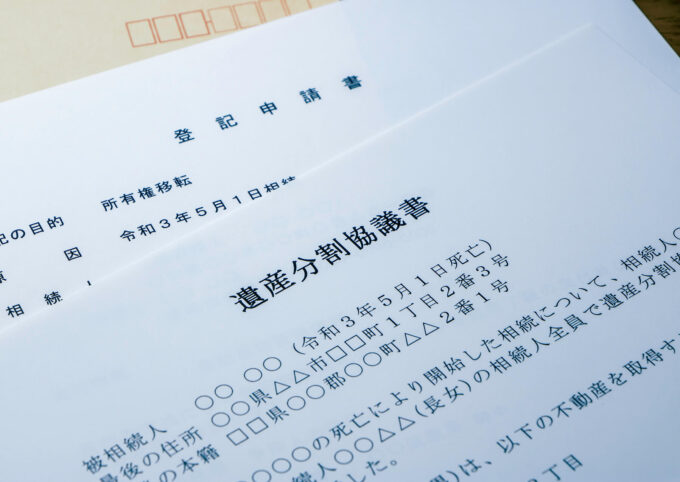
相続が発生した際、相続財産の中に、不動産の共有持分が含まれているケースがあります。これももちろん遺産分割の対象となりますが、通常の単独所有の場合と異なり、他の共有者が存在するため、いくつかの注意点があります。
共有持分であっても遺産分割は必要
共有持分であっても、被相続人名義のものであれば、遺産分割の対象となります。
不動産の共有持分に限った話をすれば、大きく分けて、次の3つのいずれかになると思います。
例えば、相続人がABの2人だけである場合、相続分は2分の1になります。これを前提にすると、
①その共有持分を相続人の一人が全部取得する
→Aが被相続人の共有持分2分の1を全て取得し、Bに対して4分の1相当の代償金を支払う。Aに代償金を支払えるだけの資力があれば問題ありません。
②共有持分だけを売却して売却金を相続分に従って分配する
→これによれば、共有問題から解放されると思うかもしれませんが、現実問題として買い手側からすると、共有持分だけを買い取っても、その不動産を自由に利用することができませんので、業者であっても買い手はほとんどいないでしょう。
なので、この選択がとられることは実務上ほぼありません。
③共有持分を相続分に従って分ける
→相続人ABはその不動産について4分の1ずつの共有持分を取得することになります。つまり、その不動産については、Aが4分の1、Bが4分の1、他者2分の1という持分割合で共有することになります。
共有不動産のデメリット
では、なぜ相続財産の中に不動産の共有持分があると厄介なのか、それは共有における主なデメリットと関係してきます。
自由に売却することができない
共有不動産を第三者へ売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。これは、民法253条(共有物の変更には共有者全員の同意)によるもので、不動産の処分が「物の形状または性質の変更行為」とみなされるためです。
そのため、共有者の誰か一人でも売却に反対すれば、売却を諦めるか、裁判等で解決するかのどちらかになります。
また、例えば他人へ貸し出して賃料収入を得たり、リフォームを行って将来の資産価値を高めようとする場合でも、民法252条により共有者の持分価格の過半数の同意が必要とされます。
共有持分に応じた費用を負担しなければならない
共有持分を有している以上、不動産にかかる固定資産税や維持費などは共有持分に応じて負担しなければなりません。
実際問題として、こうした共有不動産にかかる費用は、共有者の一人が立て替えて支払い、後日他の共有者に求償する(過去10年まで)ことができます。
数次相続で権利関係が複雑になることも
ご説明する都合上、シンプルな例として2分の1などの割合でお話ししましたが、共有者の一人が亡くなり、その持分が相続人へと引き継がれていくたびに、共有者はどんどん増えていき、持分割合の母数も増えていくことになります。
遺産分割した後についても考慮する必要がある
以上のように、共有名義の不動産には様々なデメリットが存在します。
そのため、相続財産の中に不動産の共有持分が含まれている場合には、遺産分割後の状況まで踏まえて検討しなければなりません。
遺産分割の結果、他の相続人や第三者とさらに共有状態が続くようであれば、その後に共有物分割手続を経て単独名義を目指すことが一般的です。
相続人固有の共有持分について
被相続人と不動産を共有していた者が相続人であって、かつ共有不動産が相続人らのみで共有となった場合(例えば、不動産が父と長男の共有名義であったが、父が死亡し、相続人母、長男、長女で共有することになった場合)は、遺産分割と同時に解決することができる余地があります。
共有者(相続人)の一人が他の共有者の持分を買い取ることで、単独名義の不動産にすることができますし、相続人全員の合意で第三者へ売却し売却代金を相続分に従って分配することも手続上可能です。
例えば、相続人の一人が他の共有者の持分を買い取ることで単独名義の不動産にする方法や、相続人全員の合意で第三者に売却して売却代金を分配する方法で合意形成できれば、終局的に解決できます。
ただし、相続人固有の共有持分(この例でいえば長男のもともとの持分)については、共有物分割手続によって解決されるべき問題であり、遺産分割協議や調停で合意ができなかった場合や審判手続に移行した場合には、遺産分割手続の中で処理できない可能性もある点に注意が必要です。
第三者と共有していた場合について
あまり多くはありませんが、被相続人が友人や企業と不動産を2分の1ずつで共有していたケースなど、共有者の一人が第三者という場合があります。
このような遺産共有持分と他の共有持分が併存する場合における共有物分割と遺産分割の関係について、最高裁判例(最判平成25年11月29日)は、
「共有物について、遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である。そうすると、遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には、遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものである」としています。
つまり、この最高裁の事例では、他の共有者(会社)が相続人から共有持分を買い取ることで、単独名義となり、支払われた代償金は遺産分割によって最終的に誰が取得するのかが確定します。
共有物分割訴訟は柔軟な解決がなされる場合が多く、企業であれば代償金の支払い能力も高いと考えられたのでしょう。
最後に
相続財産の中に共有持分がある場合は、単に遺産分割するだけで問題が解決しきらないことも多々あります。
売却するか、一旦共有状態のままにするか、誰かが買い取るかなど、ケースバイケースで慎重に検討すべきです。
こうした問題は相続人同士でトラブルになりやすく、時間や労力がかかることも少なくありません。
そのような場合には、弁護士等の専門家を早期に交えて協議を進めることで、迅速かつ円満に合意形成を図ることができます。遺産分割がなかなか進まないなど、お困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。