建物明渡の強制執行の基本的な流れ
目次
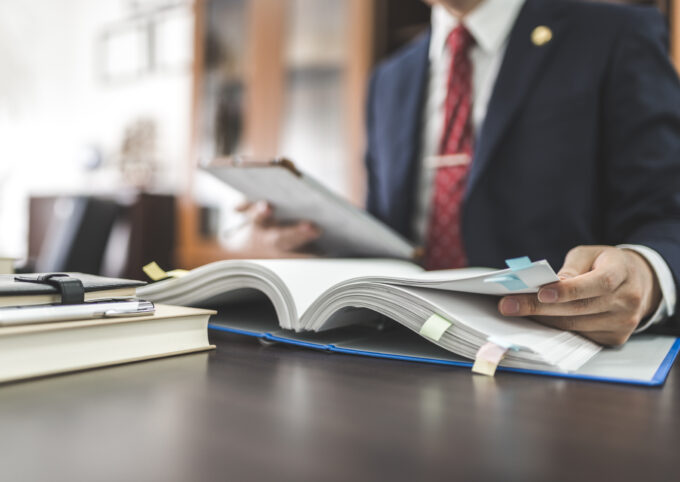
賃貸借契約で賃借人が家賃を支払わずに滞納し、交渉しても退去しない場合、貸主(賃貸人)は、訴訟によって「賃借人は建物を明け渡せ」という判決を得ることがあります。
しかし、判決が出たからといって、貸主が自ら賃借人の私物を撤去するなどの行為は許されません。いわゆる「自力救済の禁止」の原則によって、強制的に退去させるには新たな手続(強制執行)が必要です。
本稿では、建物明渡執行(建物明け渡しの強制執行)の基本的な流れを中心に、その手続と注意点について解説します。
自力救済の禁止
自力救済の禁止とは、どれほど正当な権利の回復であっても、法律で定められた手続きを経ずに自分で権利を実力行使し、強引に回復することを認めないという法律上のルールです。
賃貸人の立場からすれば、賃料を支払わない賃借人に対し、鍵を変えて入れないようにするとか、裁判所から明け渡せとお墨付きの判決が出たのだから当然賃借人の荷物を屋外へ出せるとか、賃借人は夜逃げをしたらしくそのままにしておくと次に貸し出せないからさっさと残置物を撤去してしまおうとか考えてしまうと思いますし、賃貸人の権利としてはある意味正当な行為と言えそうです。
しかし、契約上の義務を履行しない賃借人が悪いなどと一方的に決めつけて行動に移してしまうのは社会的に許されないことになります。もし自力救済が容認されれば、強い立場の者が弱い立場の者に対して一方的に行動を起こす事態に陥りやすくなり、社会秩序を乱すおそれがあります。
そこで、法は、社会秩序を保つという意味でも、たとえ正当であっても、被害回復のためには何をやってもいいというルールではなく、法律によって解決すべきであり、自らの手で権利回復をするのは禁止にすることにしたのです。
判決に従わない不法占拠者に対しては明渡執行をする
先ほどの例のように、賃貸借契約に基づき毎月の賃料を支払わなければならない賃借人がこれを長期間滞納していると、契約解除事由となります。交渉でも賃借人が出て行かない場合には、訴訟で決着をつけることになりますが、賃貸人の勝訴判決、つまり「賃借人は建物を明け渡せ。」という判決が出ても、賃借人があっさり退去しないケースも少なく有りません。建物を明け渡さない、土地を不法に占拠しているというケースは多くあります。
この場合、単に判決があるだけでは強制的に明け渡しをさせることはできないため、強制執行という手続を利用しなければなりません。これを「建物明渡執行」と呼びます。
明渡執行の基本的な流れ
強制執行手続は裁判所が管理し、「執行官」が実際に現地へ出向いて明け渡しを実現します。大まかな流れは次のとおりです。
1 申立て
2 執行官との打合せ
3 明渡催告
4 明渡の断行(強制執行の実施)
申立ての準備から申立てまで【東京地裁の場合】
明渡執行を申し立てるにあたっては、東京地裁で申立てをする場合、基本的に次の書類が必要です。
- 執行文の付された債務名義の正本
- 送達証明書
- (確定しなければ効力を生じない債務名義については)確定証明書
- 資格証明書(当事者が法人の場合)
- 委任状(弁護士に依頼する場合)
- 債務者に関する調査票
- 執行場所の案内図
- 予納金
①執行文の付与された債務名義
明渡執行を含め民事執行の申立てには、執行文の付与された債務名義の正本が必要です。
判決正本や和解調書といった債務名義には執行文を付与してもらう必要がありますが、仮執行宣言付支払督促や家事調停調書といった債務名義は単純執行文が不要です。
②送達証明書
強制執行をするには、債務者に債務名義の正本が送達されていなければなりません。これを証明するため送達証明書が必要です。
③確定証明書
債務名義の種類によっては、確定期間内に相手方が不服申立てをしなければ、その効力を生ずるとするものもあります。こうした債務名義に基づいて強制執行をする場合には、確定証明書も必要です。
④資格証明書・⑤委任状
資格証明書と委任状は必要に応じての話ですが、強制執行の申立てをする者と不法占拠者のいずれかの当事者が法人であれば、代表者事項証明書(法務局で取得)が必要ですし、申立てからの手続を弁護士に依頼するのであれば、弁護士への委任状が必要です。
⑥調査票・⑦案内図
債務者に関する調査票については、平たく言うと債務者がどういう人物で、当該物件がどういう物件なのかを執行官に知ってもらうための調査票です。調査票には、債務者の属性として粗暴性の有無や反社情報の有無、生活保護を受給中か、認知能力の有無、物件情報として住居なのか駐車場なのか、同居人はいるのかといった債権者が知っている情報を記載します。
案内図については、最寄り駅から場所までの案内図です。Googleマップで足ります。執行官は現地に行って催告や断行をします。執行官は初めて行く場所なので、案内図が必要となるのです。
⑧予納金
裁判所(執行官)に明渡執行してもらうためには、申立時に予納金を納めなければなりません。債務者1名で、対象物件が1個であれば標準的な予納金は65000円です。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ 強制執行に必要な執行文付与とは? |
申立てから打合せまで
申立てをし、事件化されたら、執行に入る前に執行官と打合せをします。
執行官との打合せでは、執行手続がスムーズにいくための質問がされます。例えば、相手方は今もそこに住んでいるのか、相手方はどのような人物か、執行業者や開錠技術者の手配は必要かなどなどです。このような質問をすることで、すでに相手方が退去しているのであれば催告する必要はありませんし、相手方が反社など抵抗が予想されるのであれば警察等に立ち会いの援助を求めることもあります。また残置物があればそれを撤去しなければなりませんので、専門にする執行補助者(執行業者)に依頼することもあり、さらに相手方の抵抗が激しく鍵をかけて籠城する可能性があるのであれば開錠技術者を手配することもあります。こうした専門業者は、執行官が紹介する形で手配することもできますし、自分で手配することもできます。いずれにしろ、執行業者等に係る費用は債権者の負担となります。
打合せから明渡催告まで
執行官に相手方(債務者)に関するより多くの情報を与えることができ、専門業者などの手配が済んだら執行官による「明渡催告」をします。催告とは、執行官が現地を訪れ、○日までに退去しないなら強制的に実施するという最後通告のようなものです。
いきなり断行しないのは、あくまで債務者が自発的に退去することを促すためです。
不法占拠している理由は様々あり、敗訴判決で出て行かなければならないことはわかっているがどうすればよいか分からず居座っているケースもあれば、退去することに断固拒否する者もいます。
ただ、どのような考えを持っているのかは、債権者も執行官も計り知れないところもあるので、一旦催告として、明渡を実行する日はこの日なのでそれまでに出て行くように言うのです。
催告から断行、そして執行の終了
催告が終わると、後は断行日を迎えるだけです。たまに、断行日前に債務者が任意で出て行くことがありますが、確実に退去してもらうことが重要ですので、係る強制執行費用をも含めて、この段階でそれに応じるかは正直なところ債権者次第でしょう。
さて、いよいよ断行ですが、基本的には物件内へ立入り、残置物等を運び出し、執行調書を作成して、手続は終わりです。
残置物に関して言うと、過去の経験上、断行日前に債務者が退去した場合であっても、きれいになっていることはまずあり得ず、ゴミや不要となった物ばかりが残されています。
価値がない動産や買い手のつかない物品は保管した上で、一定期間を経ても債務者が取りに来なければ処分されるのが一般的です。実際にはゴミ同然の品が大量に残されることも多く、その処分費用も申立人側の負担となる点に留意が必要です。
運び出された動産について、価値があると執行官が判断した場合、その場で申立人に売却し、申立人がさらに処分して現金を得るという方法があります。これは、明渡ではよく未払賃料や賃料相当損害金も併せて請求することがあるため、このような即時売却がなされるのです。即時売却しなかった(できなかった)動産については、保管した上で、後日債務者が取りに来るか(来たケースはありません。)、買い受け希望業者に売却します。
そして、最後に新しい鍵に交換して、執行調書が作成され、債権者と立会人が署名押印すれば執行手続は終了です。
最後に
以上が建物明渡執行の基本的な流れです。
債権執行や不動産競売に比べれば、簡易と思われるかもしれませんが、それは執行官との打合せが十分になされたからです。執行官からすれば、債務者のことは、自分よりも、少なくとも債権者の方が詳しいと思っているので、スムーズな断行をするためには、執行官との十分な打ち合わせがポイントです。明渡執行手続に不安な点があれば、執行官と相談しながら進めていくこともできるでしょう。
またこうした煩雑な手続きを弁護士に依頼することもできますので、お困りの方は弁護士に相談することをお勧めします。