刑事告訴における弁護士の役割
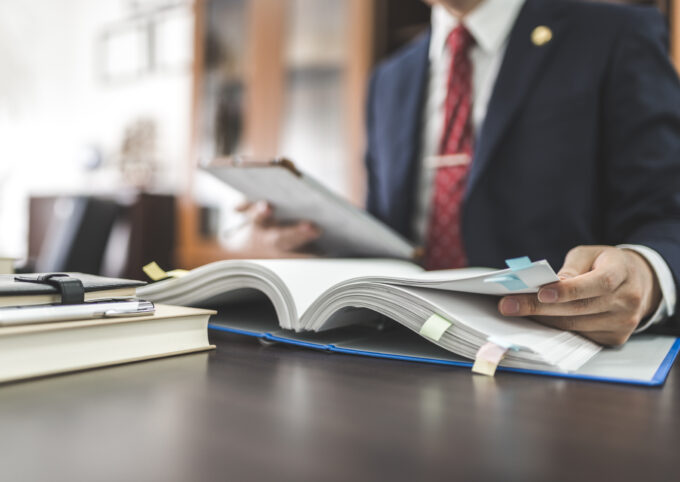
当事務所には、刑事告訴に関する次のようなご相談がとても多く寄せられています。
- 犯罪被害に遭い、刑事告訴をしたいと考えている(その場合の費用はいくらか)
- 警察に被害届や刑事告訴をしたが、証拠が少ないなどと言われ、受理してくれなかった
犯罪被害を受けた際に、刑事告訴や被害届の提出は、加害者に対して刑事責任を追及するための重要な手段です。
しかし、実務上、「証拠が不足しているから」といった理由で、事実上「告訴状を受理してもらえない」形になることが少なくありません。
確かに相談者のよくあるケースとして、証拠不十分や構成要件不充足などが理由となって受理を拒まれているようなケースも多く存在します。
他方、要式の整った告訴については捜査機関に「受理義務」がある以上、警察が形式要件を満たした告訴を恣意的に拒否することは、犯罪捜査規範にも反すると考えられます。
警察の対応が一切の根拠なく頑なに受理を拒否する行為は、犯罪捜査規範に反する対応であり、本来であればあってはならないことなのです。
弁護士が代理で提出したとしても、警察の対応は同じようにとられることが多く、犯罪被害者にとっては捜査機関に対する不信感が募るかもしれません。
もし刑事告訴を弁護士に依頼した場合に、実際に告訴が受理されるまで弁護士がどのような活動をするのか、その役割についても簡単にご紹介したいと思います。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ こんな時どうする?|被害届を出したのに警察が動かないとき |
刑事告訴とは
改めて、刑事告訴とは、犯罪被害者などの告訴権者が警察などの捜査機関に対し、犯罪被害の事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示をすることをいいます。刑事告訴は、一般的に、警察署に出向いて告訴状と証拠を提出します。
「被害届」と「刑事告訴」の法的な意味の違いとしては下記のとおりです。
- 告訴:犯罪被害者(または一定の告訴権者)が「犯人を処罰してほしい」と明確に求める意思表示。警察の受理後は捜査義務が生じるとされる。
- 被害届:犯罪被害の事実を捜査機関に申告する届出のこと。「処罰を求める意思表示」までは含まない。警察は参考資料として扱うが、告訴ほど厳格に“受理義務”は定められていないと解釈されている。
このように、被害届と異なり、告訴の方が「捜査義務が生じる」という強力な法的効果があります。
したがって、告訴が受理されたら、警察には捜査義務が発生します。
そして、警察による捜査が尽くされた後、検察官に送られるわけですが(送致)、検察官は、告訴又は告発された事件について、起訴又は不起訴の処分をしたときは、その旨を告訴人又は告発人に通知しなければならず(刑事訴訟法260条)、告訴人又は告発人から不起訴とした理由についての回答を求められた際には、その理由を告げなければなりません(刑事訴訟法261条)。
もっとも、告訴が受理されたからといって必ず逮捕や起訴になるわけではなく、逮捕するか起訴するかは捜査機関の判断に委ねられます。
刑事告訴における弁護士の役割
以上のような流れになる刑事告訴又は刑事告発において、弁護士は、大きく分けて2つの場面で犯罪被害者をサポートします。
告訴状の作成
まずは捜査機関に提出する告訴状と証拠の作成です。
告訴状に、単に、こういう犯罪被害に遭ったので、捜査・逮捕してください、と記載しても受理はしてくれません。捜査機関に速やかに受理してもらうためには、犯罪事実とこれを証明する証拠を整理・精査した上で、告訴をしなければなりません。
犯罪事実に関して、刑法が規定する各犯罪には、その犯罪が成立するための要件があります(これを構成要件と言います。)。この要件に従って、具体的な事実を記載しながら、犯罪が成立することを主張していかなければなりません。
そして、この構成要件は、基本的に条文から読み解くのですが、弁護士などの専門家でない限り、なかなか難しいと思いますし、読み解けたとしても実際にどう記載していいのかわからないこともあると思います。
証拠がなければ告訴受理までのハードルはより高くなる
そして、このような犯罪事実を証明するための証拠を整理・精査する必要がありますが、法律上、刑事告訴をするにあたっては証拠を添付しなければならない旨の規定はありません。しかし、犯罪事実を証明できる証拠がなければ、捜査機関はその告訴を受理しようとはせず、必ずと言っていいほど証拠を求められます。
そのため、犯罪事実を記載できても、それらが証拠によってきちんと裏付けられているかを精査しなければなりません。
犯罪によって、求められる証拠は様々ですが、例えば、インターネット上の投稿に対する名誉毀損であれば投稿内容がわかるスクリーンショット、詐欺罪であれば振込先口座や詐欺師とのやり取りといったものが典型的な証拠になります。
どういう証拠が必要なのかは、ケースバイケースですが、集められる証拠が少なければ、告訴受理までのハードルはより高くなります。
そのため、犯罪被害に遭った際には、できるだけ多くの証拠を集め保存しておくことをお勧めします。
弁護士が行う警察対応
告訴状と証拠が揃ったら、警察署に提出しに行くわけですが、事前に相談してアポイントを取って告訴状を一先ず提出し、協議の上、正式受理してもらいます。
そして、当然のことながら、弁護士が代理で提出しに行っても、警察は一先ずコピーを取らせてもらい、検討の上、またご連絡します。と言ってきます。
事案の緊急性があるケースだと、わかりましたとは言っていられないので、その場で受理してもらうよう警察に対して強く働きかけます(あまりにも不誠実な対応だと強く主張したり、公安委員会等に苦情を申し入れることもあります。)。
検察庁へ直接告訴状を提出する(検察官に対する告訴。「直告」(ちょっこく)と呼びます。)という方法もありますが、この方法で受理されても、特捜部が扱うような大きな事件で無い限りは通常、検察官+検察事務官の2名体制という非現実的な捜査体制で捜査されることになってしまいますので、当事務所ではなるべく警察に受理させるように働きかけます。
一方で、警察の対応からその日は受理されず後日の受理になりそうな場合でも、弁護士は定期的にその後の状況を警察に連絡をして、得た情報や状況を依頼者とも共有し、警察から追加の証拠を求められた際には依頼者に連絡するなどの対応をします。
まずは自分で動いてみるのも一つ
刑事告訴はもちろんご自身でも行うことができます。
警察に相談しても追い返される可能性が高いことを踏まえた上で、まずは自分で動いてみることも一つです。
最初から弁護士に依頼するのもアリですが、弁護士に依頼すれば、弁護士費用がかかります(それでも良く、どうしても受理してもらって警察に捜査して欲しいという相当強いお気持ちがあれば話は別です。)。また捜査機関には受理義務があるものの、弁護士に依頼すればすぐに受理されることが約束されるわけでもありません。そして、受理されれば犯人が逮捕され、確実に刑事責任を負わせられるわけでもありません。
まずはご自身で警察に相談してみて、それでも受理しない対応などであれば弁護士に相談し、場合によっては依頼するというステップで臨まれた方が良いでしょう。