遺言書でトラブルにならないために|作成方法と記載内容について
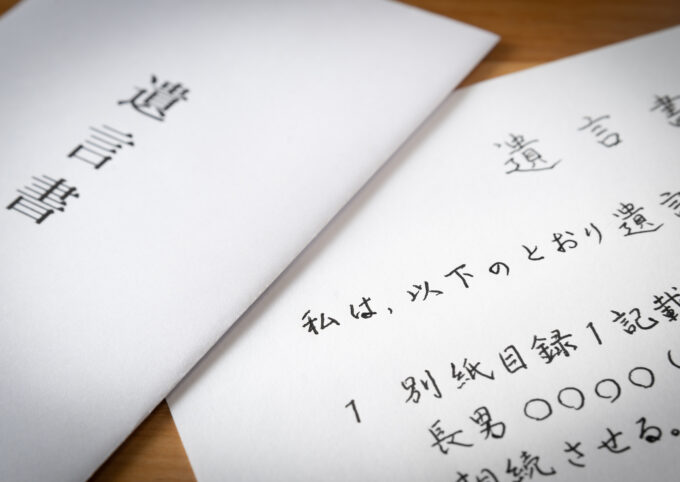
遺言書は、亡くなられた方の遺産に関する最後の意思表示とも言うこともできる、被相続人名義の財産の分け方やその他の希望を記した法律で認められた文書です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、いずれも適切な形式で作成されていれば、遺言者の意思を法的に実現する重要な役割を果たします。
しかし、一方で、形式に不備があったり、記載内容が曖昧であったりすると相続人間で逆にトラブルに発展してしまうことも実務上ありますので、遺言書を残したい方の立場から、遺言書でトラブルを回避するための作成方法と記載内容についてご紹介します。
遺言書の種類
遺言書には形式によっていくつか種類があり、種類によって作成方法も異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、被相続人が自ら全文を手書きし、最後に日付と署名を記載する形式です(民法968条)。
自筆証書遺言を作成するメリットは、気軽に作成でき、いつでも書き直しができることでしょう。また後程紹介する「自筆証書遺言保管制度」を利用しない場合には、費用が一切かからないこともメリットにあげられます。
一方で、デメリットは、民法968条が規定する法定要件を満たしていない場合には、相続人間で有効・無効の争いになりやすく、紛失などのおそれや、相続開始後に自分に不利な内容の遺言書を見つけた相続人が破棄してしまうなどのリスクもあります。
自筆証書遺言が形式的に有効とされるのは、以下の基本的な要件を具備しなければなりません。
- 財産目録を除く全文(タイトル含む)を自筆すること
- 署名と押印(認印可)をすること
- 作成年月日を記載すること(1月吉日のような記載は認められません)
自筆証書遺言保管制度
これまで自筆証書遺言は自宅内に保管されていることが多く、相続人等の利害関係者によって破棄や隠匿、改ざんなどがなされることが往々にして生じ、問題となっていました。しかし、現在は法務局で自筆証書遺言を保管する制度が設けられ、この制度を利用すれば、自筆証書遺言の紛失・亡失、破棄・隠匿・改ざんの心配はありません。自筆証書遺言を法務局で保管してもらう具体的な手続や費用については法務局ホームパージか直接法務局にお尋ねください。
共同遺言の禁止
自筆証書遺言は最も手軽に作成できるが故に、例えば、夫婦が共同して連名で遺言書を作成してしまうことがあります。しかし、こうした共同での遺言は民法で禁止されており、仮に作成してしまった場合は無効となります(民法975条)。
公正証書遺言
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が正確に作成し、公証役場で保管する形式です(民法969条)。
公正証書遺言のメリットは、何といっても信頼性と有効性の高さでしょう。公証人は、元裁判官や元検察官などが退官後に就くことの多い役職であり、彼らは法律の専門家です。
そのため、形式的な部分はもちろんのこと、内容でも相続人間での争いはまず起こりにくいです。
一方で、公証人に作成してもらいますので、作成費用が発生します(証人2名を用意できない場合は公証役場で紹介してもらうことができますが、その場合は別途費用が発生します。)。
また、作成にあたっては、事前に必要書類の提出や公証人による遺言公正証書(案)を公証人と協議・修正しながら行い、最終的に公証人や証人2名の面前で遺言の内容を口頭で告げる必要がありますので、今日明日作成・完成できるものではありません。事前に公証役場を予約しておく必要があります。そのため、時間的余裕が必要となることが多いです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう形式です(民法970条)。
秘密証書遺言は、平たく言いますと、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な要素があり、メリットは、公証人が遺言書の封紙面を作成しますので、自筆証書遺言では生じうる偽造や変造を防ぐことができます。
他方、公証役場には遺言書の封紙だけが保管され、作成時においても公証人は内容面には触れませんので、内容に関しては不安が残ることがあります。また秘密証書遺言も公正証書遺言同様、費用が発生します(証人2名の立会が必要になりますので、ご自身で集められない場合、その費用も発生することがあります。)。
危急時遺言
危急時遺言は、遺言者の生命に危機が迫り、すぐに他の形式による遺言書を作成することができない状態の時に作成する遺言書です(民法976条)。緊急性が高いため、口頭で遺言を残し、証人が代わりに書面化します。
危急時遺言の効力を生じさせるためには、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、その確認を得る必要があります(民法976条4項)。さらに、家庭裁判所は、危急時遺言が遺言者の真意であることを確認しなければなりません(民法976条5項)。実際に裁判所の職員が病院まで遺言者の方に会いに来たり、証人が裁判所に後日呼び出され裁判官と面接して当時の様子を尋ねられます。
危急時遺言は裁判所の取扱い数も事例としても非常に稀有であり、当事務所でも1年に一回あるかないかくらいの件数の取扱歴しかございません。
法定遺言事項と付言事項
法定遺言事項
遺言書作成については、方式が厳格であるだけでなく、遺言できる内容についてまで法律で定められています。
遺言書の効力で指定できることとしては、主に以下のようなものがあります。
- 誰にどの財産をどれだけ相続させるか(相続分の指定や遺産分割方法の指定)
- 最長5年を超えない期間での遺産分割の禁止(期間の指定がない場合は5年間の効力を有する)
- 推定相続人の廃除又はその取消し
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺留分侵害額請求の負担方法
- 法定相続人以外の第三者への遺贈
- 生命保険金受取人の変更
- 信託の設定
- 認知
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
- 遺言執行者の指定又はその委託
- 祭祀を主宰すべき者の指定
付言事項
法定遺言事項とは異なり、法律上の効果は生じませんが、遺言書に記載できる事項を付言事項といいます。言うなれば、個人的なメッセージであって道徳的な意味合いになります。
最後の想いを伝える場でもありますので、伝えることで相続トラブルを回避できたり、円滑な相続手続ができるなどが期待できます。
主な記載内容としては、葬儀の方法、遺品処分に関すること、遺産分割方法指定の主旨、会社後継者の指名、ペットの世話などがあります。
記載の際の注意点
ここまで法律上に定められた形式、内容についてご紹介しましたが、いずれの場合でも、遺言書を作成するにあたっての注意点があります。
1 形式の厳守
遺言書は、形式的な不備があると無効となるおそれがあります。特に自筆証書遺言では問題になりやすいので、注意が必要です。
2 遺留分に配慮する
法定相続人には相続財産から最低限得られる遺留分が法律上保障されており、それを侵害する内容は、遺言の効力発生後(遺言者の死亡後)、相続人間で特に争いとなりやすい問題です。
3 定期的な見直し
遺言書作成後、財産や家族構成に変化があった場合は、遺言書の内容を見直しましょう。必要に応じて再度作成しなければならないケースもあります。なお、遺言書が複数存在する場合であって、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ(民法1023条)、前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であっても、差支えありません。
4 専門家によるサポート
弁護士や司法書士、公証人のサポートを受けながら、法的に問題がない内容の遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書の効力を高めるために
遺言書の効力を高めるためには、確実性のある公正証書遺言であればまず形式の不備のリスクはありません。公正証書遺言以外の遺言であれば、安全かつ確実に保管しましょう。自筆証書遺言は保管制度を積極的に利用しましょう。その他にも法的拘束力はありませんが、付言事項を活用することで死亡後の相続争いを回避しやすくなります。
最後に
遺言書の記載内容は、相続トラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に実現するための鍵となります。形式や内容に不備がないよう、しっかりと準備しましょう。専門家のサポートを受けながら進めることで、より確実な遺言書を作成することができます。
遺言書の作成でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ 危急時遺言について~遺言者が死亡の危険に迫られている場合には、口頭での遺言が出来ます |