営業秘密が持ち出されたときの対応と刑事告訴の実務
目次
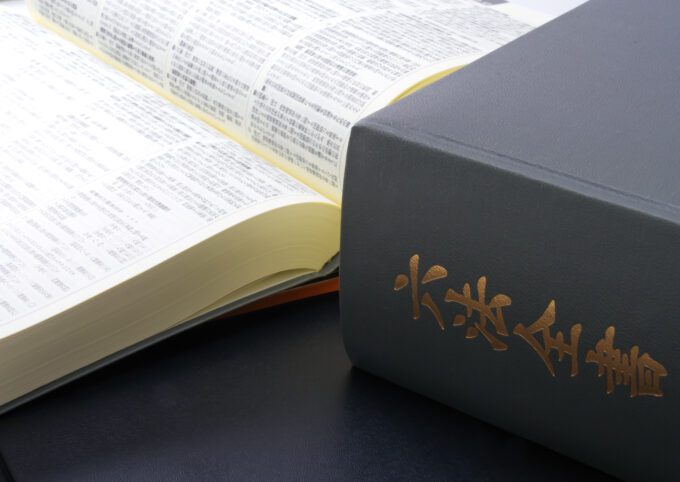
はじめに
企業の営業に関する秘密が持ち出された、自社商品と似たロゴやパッケージが使われているなど、不正競争防止法に関するトラブルとなった際に、多くの企業がまず民事的な差止請求や損害賠償請求を検討されることでしょう。
しかし、不正競争防止法は民事措置だけでなく、特定の不正競争行為に対して刑事罰を規定しており、これらの行為については刑事告訴を行うことも可能です。
これまでもコラムでご紹介した通り、刑事告訴は単なる被害の報告である被害届とは異なり、「犯人の処罰を求める意思表示」を伴うため、捜査機関には原則として捜査義務が生じます。
しかし、現実には告訴状が容易に受理されるわけではなく、捜査機関が事件として立件するには高いハードルが存在します。
本稿では、不正競争防止法の概要を改めて確認した上で、どのような場合に刑事告訴が可能となるのか、実際に告訴を行う際の実務上のポイントや、弁護士に依頼するメリットについて、法的な観点からさらに掘り下げて解説します。
不正競争防止法とは
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争環境を確保し、これに関する国際約束を遵守することで、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です(不正競争防止法1条)。
不正競争行為の類型と刑事罰の対象
以下に、主な不正競争行為の類型と、刑事罰の有無を示します。
- 周知表示混同惹起行為(2条1項1号): 広く認識されている他人の商品等表示(商品名、社名、ロゴ等)と同一・類似の表示を使用し、混同を生じさせる行為。
- 刑事罰:あり (5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方)
- 著名表示冒用行為(2条1項2号): 他人の著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為。混同の有無は問いません。
- 刑事罰:あり (5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方)
- 商品形態模倣行為(2条1項3号): 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、貸渡、展示、輸出入等する行為(製造日から3年を経過した商品は除く)。
- 刑事罰:あり (5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方)
- 営業秘密侵害行為(2条1項4号~10号): 窃盗、詐欺、強迫その他の不正な手段による営業秘密の取得、取得した営業秘密の使用・開示、不正取得品であることを知っての取得・使用・開示、従業員等からの不正開示の取得・使用・開示など、営業秘密に関わる一連の不正行為。
- 刑事罰:あり (10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金、またはこれらの両方 – 罰則が特に重い)
- 限定提供データ不正取得等行為(2条1項11号~16号): 特定の者に提供されるデータ(限定提供データ)を、不正な手段で取得し、使用・開示等する行為。
- 刑事罰:なし
- 技術的制限手段回避装置等提供行為(2条1項17号, 18号): コンテンツの視聴等を制限する技術的制限手段を回避するための装置やプログラム、役務等を提供する行為。
- 刑事罰:あり (5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方)
- ドメイン名に関する不正行為(2条1項19号): 不正の利益目的等で、他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為。
- 刑事罰:なし
- 原産地、品質等誤認惹起行為(2条1項20号): 商品や役務の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等を誤認させるような表示や広告を行う行為。
- 刑事罰:あり (5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方)
- 信用毀損行為(2条1項21号): 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為。
- 刑事罰:なし (ただし、刑法の名誉毀損罪等に該当する可能性はある)
- 代理人等の商標冒用行為(2条1項22号): 国際条約加盟国における商標権者の代理人等が、正当な理由なく権利者の承諾なしにその商標を使用する行為。
- 刑事罰:なし
上記リストからわかるように、刑事告訴が可能なのは、主に営業秘密侵害、周知・著名表示冒用、形態模倣、技術的制限手段回避装置提供、原産地・品質等誤認惹起に関する行為です。
特に営業秘密侵害行為に対する罰則は、不正競争防止法の中でも最も重く設定されています。
また、不正競争防止法には両罰規定(22条)があり、法人の代表者や従業員等がその法人の業務に関して上記の刑事罰の対象となる行為を行った場合、行為者だけでなく、その法人に対しても罰金刑が科されます。
営業秘密侵害行為の場合、法人には5億円以下の罰金刑が、さらに国外で使用された場合は10億円以下の罰金刑が科される可能性があり、企業のコンプライアンス体制の重要性が強調されています。
営業秘密に関するトラブルが多い背景と法的課題
近年、営業秘密の持ち出しに関するトラブルは増加傾向にあります。これは、終身雇用制度の崩壊や転職、フリーランスといった多様な働き方が浸透し、従業員の流動性が高まったことが背景にあると考えられます。
転職先の企業や自らの事業でこれまでの経験やノウハウを活かそうとする際に、前職で知り得た営業秘密に安易に手を出してしまうケースが少なくありません。
営業秘密侵害で刑事告訴を目指す場合、法的に乗り越えるべきハードルがいくつか存在します。
特に、後述する「営業秘密」の要件を満たすこと、そして実際に不正な取得や使用、開示といった「実行行為」が行われたことを、刑事裁判で有罪とするに足る「証明力のある証拠」に基づいて立証する必要があります。
デジタルデータの持ち出しの場合、取得行為そのものの立証は比較的容易な場合もありますが、その後の「使用」や「開示」の事実を具体的に立証することは、痕跡が残りにくい場合もあり、困難を伴うことがあります。
刑事告訴が可能な行為と手続の概要
不正競争防止法違反で刑事告訴ができるのは、前述の通り刑事罰が規定されている行為に限られます。刑事罰のない行為に対しては、告訴はできませんが、民事訴訟を通じて差止請求や損害賠償請求を行うことは可能です。
刑事告訴の手続きは、一般的に以下のような流れで進みます。
- 告訴の検討・準備: 被害事実、被告訴人(犯人)の特定、不正競争防止法上のどの類型の行為に該当するか、刑事罰の対象かなどを検討します。
- 証拠収集: 不正競争行為の事実、それによって生じた被害、そして法が定める要件(特に営業秘密の3要件など)を満たすことを示す客観的な証拠を収集します。
- 告訴状の作成: 告訴の趣旨(犯人の処罰を求めること)、告訴事実(いつ、誰が、どのような不正競争行為を行ったか)、告訴事実を裏付ける証拠などを記載した告訴状を作成します。告訴状には、被告訴人が行った行為が不正競争防止法〇条〇項〇号の罪にあたるという法的評価を明確に記載する必要があります。
- 告訴状の提出: 管轄の警察署または地方検察庁に告訴状を提出します。
- 捜査機関による判断(受理・不受理): 提出された告訴状に基づき、捜査機関は告訴状の形式的な要件や、記載された事実が犯罪を構成する可能性があるか、証拠はあるかなどを検討し、告訴を受理するか否かを判断します。前述の通り、特に証拠が不十分な場合や、単なる民事トラブルと判断される場合など、不受理となるケースも少なくありません。告訴が受理されるためには、告訴状の完成度だけでなく、事前に捜査機関と十分に協議し、事件性や証拠の十分性について理解を得ておくことが実務上非常に重要となります。
- 捜査: 告訴が受理されると、捜査機関による本格的な捜査(被告訴人の取調べ、証拠品の押収・分析、関係者の事情聴取など)が開始されます。
- 送致: 捜査が終了すると、事件は検察庁に送致されます。
- 検察官による判断(起訴・不起訴): 送致された事件について、検察官は被告訴人を刑事裁判にかけるべきか(起訴)、あるいは不起訴とするか(証拠不十分、情状などを考慮)を判断します。
営業秘密として認められるための要件と立証の難しさ
不正競争防止法における「営業秘密」とは、以下の3つの要件を全て満たす技術上または営業上の情報であると定められています(不正競争防止法2条6項)。刑事告訴においてこの要件を満たすことを立証することは、極めて重要です。
- 秘密管理性: 情報が秘密として管理されていること。
- 単に「社外秘」と書かれているだけでは不十分な場合があり、従業員に対して当該情報が秘密であることが認識できるよう、客観的に管理されている必要があります。具体的な例としては、アクセス制限(パスワード設定、保管場所の限定)、秘密保持に関する規程や誓約書の整備、情報の重要度に応じた管理策の実施などが挙げられます。誰でも自由にアクセスできる状態の情報は、秘密管理性があるとは認められません。リモートワーク環境やBYOD(Bring Your Own Device)が普及する中で、デジタル情報の秘密管理性をいかに担保・立証するかが課題となる場合があります。
- 有用性: 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること。
- 現在実際に使用されている必要はなく、将来的な事業活動にとって客観的に価値のある情報であれば認められます。顧客リスト、製造ノウハウ、価格データ、新規事業の計画、経営戦略などが含まれます。市場に出回っている公知の情報や、単なる個人的なアイデアは有用性があるとは認められません。
- 非公知性: 公然と知られていないこと。
- 情報の管理者の管理下以外では一般に入手できない状態にあることを指します。書籍、論文、インターネット等で容易に入手できる情報は非公知性があるとは認められません。秘密管理性がしっかりしている情報は、非公知性も認められやすい傾向にあります。
これらの要件を満たすことを立証するためには、情報がどのように管理されていたかを示す証拠(社内規程、アクセスログ、誓約書、管理場所の写真など)、情報の有用性を示す証拠(情報の利用によって得られた成果、専門家の意見など)、そして情報が公になっていなかったことを示す証拠(公開情報の調査結果など)などを集める必要があります。
さらに、被告訴人がこの営業秘密を「不正な手段」で「取得」「使用」「開示」したという「実行行為」の事実と、その行為が不正の競争の目的や不正の利益を得る目的、あるいは権利者に損害を加える目的をもって行われた可能性が高いことを示す必要があり、これらの立証は容易ではありません。特に、取得行為の痕跡が消去されている場合や、使用・開示の事実が外部から見えにくい形で行われている場合など、状況証拠を積み重ねて立証する必要が出てきます。
刑事告訴を成功させるための実務上のポイント
不正競争防止法違反、特に営業秘密侵害で刑事告訴を受理してもらうためには、以下の実務上のポイントを押さえることが重要です。
- 告訴対象行為の特定と要件充足性の確認: 被告訴人の行為が、不正競争防止法上の刑事罰の対象となるどの類型の不正競争行為に該当するのかを正確に特定し、その行為の構成要件(特に営業秘密侵害における秘密管理性、有用性、非公知性など)を立証できるかを事前に厳密に検討します。
- 十分かつ質の高い証拠の準備: 告訴状提出前に、不正行為の事実、被害の状況、そして法が定める要件を満たすことを示す客観的で証明力の高い証拠を可能な限り収集します。証拠が不十分なまま告訴状を提出しても、受理される可能性は極めて低くなります。
- 捜査機関との事前の丁寧な協議: 告訴状を一方的に提出するのではなく、事前に管轄の警察署や検察庁に相談を持ちかけ、事件の概要、収集した証拠、告訴したい理由などを丁寧に説明し、捜査機関の理解を得る努力をすることが、受理に向けた第一歩となります。不正競争防止法違反は専門性が高いため、捜査機関に事案の特殊性や重要性を的確に伝えることが求められます。
- 告訴状の正確かつ具体的な記載: 告訴状には、いつ、どこで、誰が、何を、どのように行ったのか、そしてその行為がなぜ不正競争防止法に違反するのかを、収集した証拠に基づいて具体的に記載する必要があります。抽象的な表現や推測に基づく記載では、捜査機関は動きにくいでしょう。
- 諦めない姿勢: 一度告訴状が受理されなかったとしても、諦めずに証拠を追加収集したり、告訴状の内容を修正したりして、再度働きかける粘り強さが重要となる場合もあります。
弁護士に依頼するメリット
不正競争防止法違反、特に営業秘密に関する刑事告訴は、その法的要件の複雑さ、必要な証拠の特殊性、そして捜査機関に受理してもらうための実務上のハードルの高さから、弁護士の専門的な知識と経験が不可欠です。弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
- 複雑な法的論点の整理と告訴可能性の判断: 不正競争防止法の専門的な要件(営業秘密の3要件など)を満たすか否かを法的に厳密に判断し、告訴が成功する見込みがあるかを冷静に評価してもらえます。無闇に告訴を行うことを避け、労力や時間を無駄にするリスクを低減できます。
- 的確な証拠収集のアドバイスと支援: どのような情報が証拠として有効か、どのように収集すればよいかなど、専門的な観点からアドバイスを受けられます。事案によっては、フォレンジック調査など専門業者と連携した証拠収集のサポートも期待できます。
- 受理されやすい告訴状の作成: 不正競争防止法の構成要件を正確に踏まえ、かつ捜査機関が受理しやすいように、事実関係、証拠、法的評価などを整理し、説得力のある告訴状を作成してもらえます。
- 捜査機関との交渉・調整: 告訴状提出前の相談や、提出後の捜査機関からの問い合わせに対して、代理人として対応してもらえます。捜査機関の疑問点や要望に対して、法的な根拠に基づいた適切な説明を行うことで、受理に向けたハードルを下げることができます。
- 告訴受理後のサポート: 告訴が受理された後も、捜査の進捗状況を確認したり、必要に応じて追加の証拠や情報を提供したりするなど、捜査への協力を円滑に進めるサポートが受けられます。
- 示談交渉への対応: 捜査の過程で加害者側から示談の申し入れがあった場合、弁護士が代理人として、被害額の回復や再発防止策など、依頼者の意向を踏まえた適切な条件での示談交渉を進めることができます。
- 民事措置との連携: 刑事告訴と並行して、または刑事告訴が難しい場合でも、民事での差止請求や損害賠償請求を検討することができます。弁護士であれば、刑事と民事の両面から最も効果的な解決策を立案し、連携して手続きを進めることが可能です。
不正競争防止法違反の被害に遭われた際は、まずは早期に不正競争防止法や企業法務に詳しい弁護士にご相談されることを強くお勧めします。専門家のアドバイスを得ることで、採り得る手段、必要な対応、そして告訴の可能性と見通しを正確に把握し、適切な対応をとることができます。