刑事告訴の依頼:弁護士と行政書士のどちらにするべきか。
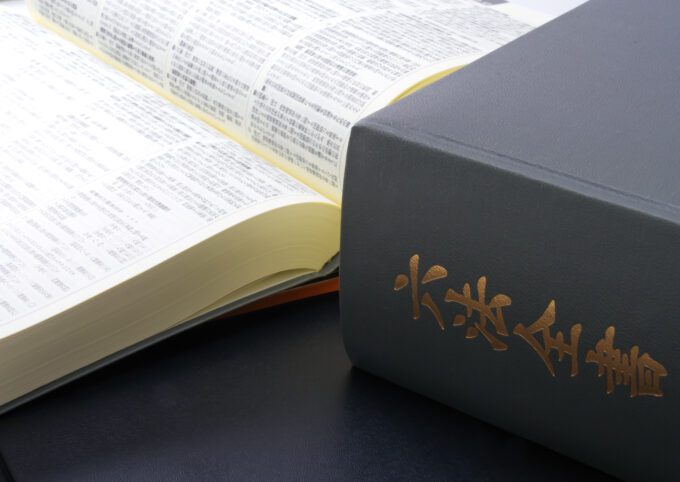
犯罪被害に遭い、捜査機関に対して刑事告訴をしようと考えたとき、もちろんご自身で告訴状を作成し、適切な証拠を収集・整理することができれば、ご自身でも刑事告訴をすることができます。
しかし、当事務所に寄せられる刑事告訴に関するご相談の中には、「警察に告訴状や被害届を提出しようとしたが、受理してもらえなかった」というケースが少なくありません。
このような場合、または専門的知見に基づいて質の高い告訴状を作成してもらいたいという場合には、弁護士への相談を検討される方が多いでしょう。また、選択肢の一つとして、行政書士への依頼を考える方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、刑事告訴を専門家に依頼する際に、弁護士と行政書士のどちらを選ぶべきか、それぞれのメリット・デメリットや役割の違いについて解説します。
なお、警察が告訴の受理を渋る理由などについては、別のコラムでもご紹介していますので、是非ご参照ください。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ なぜ?警察が刑事告訴の受理を断る理由 |
刑事告訴における弁護士と行政書士の違い
業務範囲の違い
- 弁護士 弁護士は、弁護士法に基づき、法律問題全般について代理人として活動することができます。刑事告訴に関して言えば、弁護士は以下の活動を包括的にサポートできます。
- 告訴状の作成・提出: 事案を法的に分析し、犯罪構成要件を充足する告訴状を作成し、代理人として警察署に提出します。
- 捜査機関との折衝: 警察や検察に対し、受理に向けた説明、証拠の追加提出、捜査の進捗確認、意見の表明などを行います。
- 示談交渉: 被疑者(加害者)側との示談交渉を代理人として行い、被害回復を目指します。
- 捜査・公判段階のサポート: 捜査段階での事情聴取への同行、検察審査会への不服申立て(不起訴の場合)、刑事裁判における被害者参加制度の利用支援など、刑事手続全般にわたって被害者をサポートします。
- 行政書士 行政書士は、行政書士法に基づき、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」の作成代理を主な業務とします。刑事告訴に関しては、以下の業務が中心となります。
- 告訴状の作成: 依頼に基づき、告訴状の書面を作成します。
- 証拠の整理: 告訴状に添付する証拠の整理を補助します。
ただし、行政書士ができるのは原則として書類作成とその提出代行(事実上の使者としての活動)までです。
警察署への提出後の捜査機関との交渉や、法律事件に関する法律事務である示談交渉は、弁護士法第72条で禁止されている非弁行為に該当する可能性が極めて高く、行政書士が行うことはできません。
費用の違い
- 弁護士 弁護士に依頼する場合、契約内容(どこまでの業務を依頼するか)によって費用は大きく変動します。一般的に、告訴状の作成から捜査機関との折衝、示談交渉までを一括して依頼する場合、着手金と成功報酬金(告訴受理、起訴、示談成立など成果に応じた報酬)を合わせて、数十万円から百万円を超えるケースもあります。事案の複雑さや証拠の状況、予想される業務量によって費用は異なりますので、必ず事前に見積もりを確認しましょう。
- 行政書士 行政書士に告訴状の作成のみを依頼する場合、一般的には数万円から十数万円程度が相場となることが多いようです。ただし、これも事案の難易度や作成する書類の量によって変動します。
弁護士か行政書士か、何を重視するかが大事
どちらの専門家を選択するかは、被害者の方が何を最も重視するかによって変わってきます。
- 弁護士に依頼するメリットが大きいケース
- 告訴状を確実に受理させたい。
- 警察との折衝や捜査への積極的な関与を専門家に任せたい。
- 受理後の示談交渉も一任したい。
- 複雑な事案で、法的な専門知識に基づくサポートが不可欠。
- 不起訴になった場合の不服申立(検察審査会への申立てなど)も視野に入れている。
- 刑事裁判になった場合に被害者として関与していきたい(被害者参加制度の利用)。
- 行政書士の利用が考えられるケース
- 費用を可能な限り抑えたい。
- 事実関係が極めて単純明快で、証拠も十分に揃っている。
- 告訴状の「書式」を整えるサポートが主目的で、警察とのやり取りは自分自身で行う意思と能力がある。
刑事告訴は弁護士が適任である理由と行政書士の限界
告訴状を作成し提出するだけであれば、理論上はご自身でも可能です。しかし、多くの場合、告訴状を提出するのは、加害者に刑事責任を負わせ、正当な処罰を受けてほしいという強い思いがあるからでしょう。そのためには、以下の点が極めて重要になります。
- 受理されやすい告訴状の作成: 犯罪構成要件を充足する事実を明確に記載し、証拠と関連付けること。犯行の経緯、動機、被害の状況などを具体的に記述すること。
- 適切な証拠の収集・整理: 客観的な証拠を揃え、告訴事実を裏付ける形で提出すること。
行政書士も業務範囲として告訴状の作成を行うことはできますが、刑事手続全般の専門家ではありません。そのため、費用を抑える目的で行政書士に依頼したものの、警察の専門的な質問や指摘に対応できず、結果として受理に至らないというケースは残念ながら散見されます。行政書士も法令に基づいて告訴状を作成することはできますが、それはあくまで書面作成までであり、実際に告訴を受理させるためには、提出時の警察への法的説明や説得が不可欠な要素となります。
刑事訴訟法第241条は、司法警察員に対し告訴・告発を受けた際の書類・証拠物の検察官への送付義務を定めており、原則として捜査機関に告訴の受理義務があると考えられています。
しかし、実務上は、捜査機関の人員不足や、事件の軽重、証拠の明白性などを理由に、直ちに受理されるとは限らないのが現状です。告訴状を作成してから受理に至るまでのプロセスこそが、刑事告訴における真の困難さと言えるかもしれません。
弁護士が告訴状を提出しようとする際も、警察から「これは事件化が難しい(どうせ不起訴になるから意味がない)」「証拠が不十分だ」「被害発生から時間が経過しすぎている」「被害が軽微である」といった理由で、受理に消極的な姿勢を示されることがあります。これらは、直ちに受理を拒否する正当な理由とは言えない場合が多いです。 しかし、このような状況で、法的知識や交渉経験のない方がご自身で反論し、受理を勝ち取るのは容易ではありません。弁護士であれば、警察の指摘に対し、法的根拠に基づいて反論し、事件の重要性や捜査の必要性、証拠の価値などを具体的に説明することで、警察の理解を得やすくなります(ただし、弁護士に依頼すれば必ず受理されるというわけではありません)。
一方で、行政書士は、たとえ刑事手続に関する知識を有していても、弁護士法により法律事件に関する交渉や鑑定(法的な判断)を行うことは業務としてできません。そのため、警察に対して法的根拠に基づいた強い働きかけや説得を行うことには限界があります。
最後に
ここまで、刑事告訴を依頼する場合に弁護士が適任である理由と、行政書士の業務範囲の限界についてご説明しました。
犯罪被害に遭われた方が、加害者に対する正当な処罰を求め、ご自身の権利を回復するためには、刑事告訴という手段が有効な場合があります。
その際、弁護士のサポートを得ることで、告訴状が受理されやすくなるだけでなく、その後の捜査が速やかに開始され、最終的に加害者が適正な刑事責任を負う可能性、そして被害回復が実現する可能性が高まります。
刑事告訴でお困りの際は、諦める前に一度、刑事事件に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めします。事案の内容や証拠の充実度から、そもそも刑事告訴が受理される見込みがあるのか、どのような準備が必要かなどについて、具体的なアドバイスを受けることができます。