特別受益と寄与分
目次
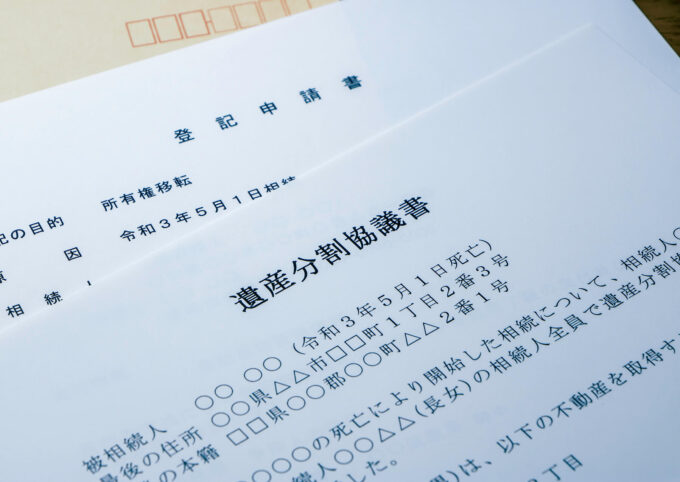
典型的な例として、被相続人の配偶者は既に先立って亡くなっており、被相続人の相続人としては長男次男の2人の子供だけである事案で考えてみましょう。
被相続人は生前長男に結婚祝として1000万円を贈与し、次男には何も贈与しませんでした。その後被相続人の死亡と同時に相続が開始し、被相続人の相続財産は2000万円ありました。共同相続人である長男と次男は、相続財産2000万円を遺産分割し、各自法定相続分2分の1の割合で1000万円ずつ取得することになりました。そうすると、長男が取得した金額は被相続人の生前に贈与を受けた1000万円を加えた計2000万円、一方次男が取得した金額は遺産分割による1000万円、ということになり、不公平を生じます。
特別受益とは
民法は、このような不公平を是正するため、被相続人から、特定の相続人(長男)が生前に特別な利益を受けたような場合の処理として、今回の例で言えば、長男への生前の1000万円の贈与額を相続財産2000万円に計算上加算して、合計3000万円を「相続財産」とみなして遺産分割を行うことに定めています。この特定の相続人(長男)が生前に特別な利益を受けたことを、特別受益と言います(民法903条)。
したがいまして、特別受益とは、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合、その受けた特別な利益のことを言います。
特別受益の対象は4つ
特別受益の対象となるのは、条文上、遺贈、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与になります。抽象的で、裁判実務上でも争点となるところもありますので、順に記します。
遺贈
遺贈とは、遺言によって特定の人(相続人や孫、お世話になった人など)に財産を譲ることです。特定の財産について遺贈をすると、その財産は遺言者が亡くなったのと同時に、確定的に特定の人(受遺者といいます。)のものになりますので、遺産分割の対象にはなりませんが、特別受益の対象になり得ます。
婚姻のための贈与
子の結婚に際し、結納金や持参金などの財産を贈与することです。ただし、特別受益は相続人間の不公平を是正するための制度ですので、全ての相続人に同程度の贈与があった場合などは特別受益とされない可能性があります。
養子縁組のための贈与
婚姻のための贈与と同様に、養子に入る場合や迎える場合に持参金などの財産を贈与することです。
生計の資本としての贈与
裁判実務上、特に争いになるのは、生計の資本としての贈与であったかどうかです。
典型例として、商売を始める子に対する開業資金や、農業を営む子に対する農地贈与、子の住宅購入費など、一般的な範囲として、受贈者(特別受益を受け取った人)の生活基盤になり得る財産上の給付は生計の資本としての贈与と認められやすいです。また、親が子の借金を肩代わりした場合や、親から子への借地人名義を変更したような場合、事業用資産を贈与した場合も特別受益にあたる可能性が高いです。
判断基準と要素
生計の資本としての贈与という曖昧かつ抽象的ゆえに、その判断はどのようにするかについては、一般的に、その贈与が親族間の扶養としての範囲を超えるかどうかで判断されます。
そして、判断要素となり得るのは、贈与された財産の価額、贈与の趣旨、被相続人の経済的状況などになります。
従いまして、高額の金員の贈与や、学費であっても、家庭や社会の環境によっても異なりますが、海外長期留学費用というような場合は、他の相続人との公平さや家庭状況などを総合的に考慮して、特別受益にあたる可能性があります。
特別受益の持戻し
特定の相続人に対する特別受益が認められた場合、遺産分割の際に、その特別受益も計算に入れることで、相続人間の不公平さを解消します。これを特別受益の持戻しと言います。
冒頭の例で言えば、長男が生前に受けた1000万円を相続財産2000万円に加えて(持ち戻して)合計3000万円にすることです。持戻しを行った上で3000万円を兄弟2人で半々に分ければ、一人1500万円ずつになり、公平だということになります。
持戻しの免除
ただし、被相続人が遺言などで持ち戻すことについて免除する意思表示をした時は、特別受益があったとしても、持戻しをしません。
また、特別受益の持戻し免除の意思表示がなくても、配偶者に対する一定の居住用財産の贈与の場合にはその意思表示があったものと推定します。
遺留分との関係
遺留分については、過去のコラム(遺言などで遺留分を侵害された相続人がとるべき対応)をご覧くださればと思いますが、遺留分との関係で補足的に説明しますと、遺留分の計算時には、持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分の計算に含めることができます。ただし、計算に含めることができる特別受益は、相続開始前10年以内のものに限られますので、ご注意ください。
寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいた場合、その相続人は遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度のことを言います。例えば、仕事を辞めて介護に専念したというような場合です。
※ただし、寄与分については容易に認められるものではなく、実務上、寄与分が考慮されるケースはそこまで多くはありません。
寄与分が認められるための一般的考慮要素(「特別の寄与」といえる要件)
① 相続人であること
② 対価を受け取っていないこと(あるいは、貰っていても非常に僅少なものであること)
③ 親族から通常期待されている程度を超える行為であったこと
④ その行為に専念していたこと
⑤ 長期間継続したこと
などの事情が総合的に考慮されて「特別の寄与」とまで言えるかが判断されます。
(「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定める(民法904条の2第2項))。
「特別の寄与」があったと認められないケース
代表例ではありますが、被相続人が経営する家業の手伝いや被相続人所有財産の管理、被相続人の介護をヘルパーさんなどの手伝いなしですべて自分ひとりで長年行ってきたといった場合は、寄与分が認められやすいでしょう。
しかし、一般的考慮要素を満たしていても、場合によっては寄与分が認められないこともあります。程度の問題になりますが、親族間の互助義務(民法730条)の範囲内であったり、裏付けとなる資料が乏しかったり、そもそも感情的になりやすいところではあります。
特別受益と寄与分の関係
特別受益も寄与分も認められる場合は、同時に考慮する必要があります。つまり、特別受益は相続財産に加算し、寄与分は相続財産から減算することになります。
まとめ
特別受益や寄与分は、相続人間で主張が対立することは少なくありません。何が特別受益にあたるかについては、判断が難しいところもあります。また寄与分も感情的な対立になり話し合いが進まないこともありますので、相続人間で話合いが進まない場合や、感情的対立が激しい場合には、ぜひ一度当事務所にご相談ください。