遺言書がある場合の相続手続の進め方|遺言書の発見から執行までの完全ガイド
目次
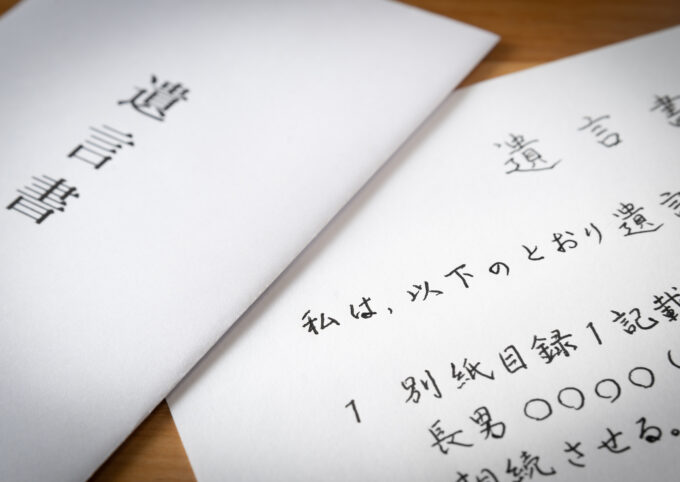
相続が発生した場合、まずは被相続人の遺言書があるのか、ないのかで相続人がとるべき対応は大きく異なります。
今回は、遺言書が「あった」場合で、かつ相続放棄をしない場合の相続手続の進め方について、順を追ってご紹介します。
遺言書がある場合の相続の大まかな流れ
被相続人に遺言書があるとき、相続人がその後に採るべき対応と大まかな流れは次の通りです。
1.遺言書を探し、その種類(方式)を確認する
2.(自宅などで保管されていた自筆証書遺言であれば)家庭裁判所に「検認」を申し立てる
3.遺言書の内容と法的な効力を確認する
4.遺言執行者がいれば相続手続を任せ、いなければ相続人全員で協力して相続手続をする
1. 遺言書の捜索と種類の確認
全てのケースで、被相続人が遺言書を書いていないわけではありません。中には、相続人が知らない間に、被相続人が生前、遺言書を作成していたケースもあります。
そこで、相続が開始したら、まず遺言書の有無を確認します。遺言書には一般的に、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3種類ありますが、実務上、ほとんどのケースが公正証書遺言または自筆証書遺言のどちらかです。
まず確認することは、遺言書がそもそも作成されていたのか、作成されていたとすれば3種類のうち、どれにあたるのか、です。
被相続人から「遺言書があるよ」と生前聞かされていた場合、あるいは被相続人死亡後、被相続人が居住していた家を捜索したところ偶然見つけた場合は別として、遺言書があるのかないのかわからない場合は、まずは
①法務局での自筆証書保管制度
または
②公証役場での公正証書遺言の照会制度
を利用して、被相続人が遺言書を作成しているか確認しましょう。
遺言書の有無がわからない場合の行動マニュアルをまとめると、以下のとおりとなります。
- 公的機関への照会
- 公正証書遺言:お近くの公証役場で、日本公証人連合会が管理する遺言検索システムを利用して、全国の公証役場で作成された遺言の有無を照会できます。
- 自筆証書遺言(法務局保管分):お近くの法務局(遺言書保管所)で、「遺言書情報証明書」の交付を請求することで、法務局に保管されている遺言の有無を確認できます。
- 自宅などの捜索 被相続人の自宅の金庫、机の引き出し、貸金庫などを探します。公的機関に照会しても見つからない「自宅保管の自筆証書遺言」が発見されることもあります。
【ポイント】公正証書遺言の謄本(写し)は、照会した公証役場だけでなく、全国どこの公証役場でも取り寄せが可能です。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ 遺言書の有無が不明な場合の、遺言書の探し方 |
2. (自宅等で保管の)自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」を
遺言書の種類によって、その後の手続きが異なります。
- 検認が必要な遺言
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、その遺言書を保管していた人や発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書の「検認」を申し立てなければなりません(民法1004条1項)。
検認は、遺言の有効性を判断するものではありませんが、不動産の相続登記や預貯金の解約といった多くの相続手続において、金融機関や法務局から検認済証明書の提出を求められるため、事実上、検認を済ませなければ手続きを進めることが困難になります。 - 検認が不要な遺言
①「公正証書遺言」と②「法務局で保管されていた自筆証書遺言」は、偽造・変造のおそれが極めて低いため、検認手続きは不要です(民法1004条2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
3. 遺言書の効力と内容の確認
遺言書が法的に有効か、その内容が実現可能かを確認します。
なぜなら、民法上、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言には、遺言書として効力に必要な要件が下記のように定められています。
- 自筆証書遺言
形式面で「全文、日付、氏名の自署」と「押印」があるか(民法968条1項)、加除訂正が適切な方式で行われているか(同条3項)などを確認します。要件を欠くと遺言自体が無効になる可能性があります。
別紙として目録を添付する場合は、目録に自書する必要はありませんが(パソコンで作成可)、目録のページ毎に署名と印を押さなければなりません(同条2項)。自筆証書遺言の内容に関して、被相続人が加除訂正をした箇所があれば、遺言書が、その場所を指示し、変更した旨を付記(署名)しており、かつその変更箇所に印が押されていなければ効力は生じません(同条3項)。また自筆証書遺言の内容に関しては、曖昧に記載されていることもありますので、相続トラブルのもとになることもあります。必要に応じて、弁護士等に相談することをお勧めします。 - 公正証書遺言
公証人が関与して厳格な手続きで作成されるため、形式的な不備で無効になることはほとんどありません。
内容が曖昧であったり、実現が困難な場合は、相続トラブルの原因となります。不安な点があれば弁護士などの専門家に相談しましょう。
4. 遺言執行者による相続手続(いれば相続手続を任せ、いなければ協力して相続手続を行う)
内容及び効力に関して特に問題なければ、具体的に遺言書の内容に従った相続手続を行っていくことになります。
次に、誰が手続をするのかですが、遺言書に遺言執行者(遺言内容を実現する役割を担う人)が指定されていて、その遺言執行者が就任を承諾した場合は、原則として遺言で指定された「遺言執行者」が手続を行います。
- 遺言執行者がいる場合
遺言執行者が就任を承諾すれば、その執行者が預貯金の解約や不動産の名義変更など、遺言内容の実現に必要な一切の行為を行う権利と義務を負います(民法1012条)。他の相続人は遺言執行者の業務を妨害してはなりません(民法1013条)。 - 遺言執行者がいない場合
遺言で指定がない場合や、指定された人が就任を断った場合は、相続人全員で協力して手続きを進めます。相続人の中から代表者を決めて進めることもできますし、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることも可能です(民法1010条)。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ 遺言執行者は何ができ、何をすべきか【遺言執行者の権限について】 |
遺言書がある場合の注意点
検認手続は、遺言の有効・無効を判断する手続ではない
検認を申し立てると、相続人に対し裁判所から検認期日が通知されます。そして、検認期日に出席した相続人に対し、遺言の存在と内容を知らせ、日付、被相続人の署名など検認期日現在における遺言書の状態を明らかにして、その後の偽造変造を防止するための手続です。
そのため、検認済証明書があるからその遺言書は有効である、とよく勘違いされる相続人がいますが、上記の通り、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認しなければ罰則を受けることも
自筆証書遺言は、検認手続をしなければなりませんが、これを怠ったり、検認を経ないで執行したり、密封されているものを勝手に開封してはなりません。検認しなくても罰則は受けないと思われている人もいるかもしれませんが、民法では、これらに違反した場合は、5万円以下の過料に処せられる旨規定されています(民法1005条)。
偽造・変造・破棄・隠匿行為は相続権を失う可能性も
自筆証書遺言を見つけた人が勝手に封を切って内容を確認したところ、自分に不利益な内容であったから、その遺言書を破り捨てたり隠した場合、その他遺言書の内容を偽造・改ざんした場合は、相続権を失い、相続人となることができない可能性があります(民法891条5号)。公正証書遺言や秘密証書遺言では起こり得ませんが、自筆証書遺言では起こり得ることです。封がされているなら速やかに検認をするべきですし、封がされていなくて中身を見て不利益な内容であっても偽造・変造・破棄・隠匿行為をしてはなりません。
遺言書に記載のない相続財産は別途遺産分割協議が必要
遺言書で全ての財産の行き先が指定されているとは限りません。記載漏れの財産が見つかった場合、その財産については相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が相続するかを決める必要があります。
また、遺言で財産を受け取るはずだった相続人が相続放棄をした場合、その財産は他の共同相続人に帰属することになります。その財産の分け方について、改めて相続人全員による遺産分割協議が必要になることがあります。
複数の遺言書がある場合は、最新の日付のものが有効
2通以上の遺言書が見つかる場合もあります。前の遺言と後の遺言の内容で抵触する部分があれば、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされるので(民法1023条1項)、この場合、最新の日付の遺言書が有効となります。抵触しない部分についての遺言書は、その部分に限り有効となりますので、内容次第では、複数の遺言書が効力を有するケースもあり得ます。