債権未回収に備える代物弁済予約とは
目次
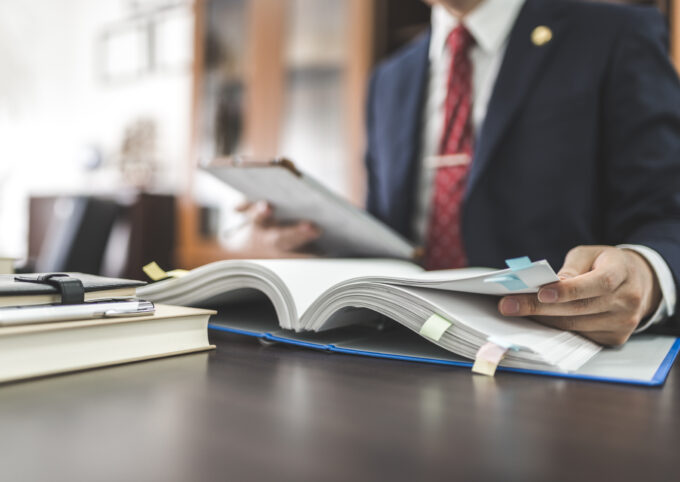
債務者に対して債権を有する債権者にとって、債権を回収できなくなるという事態は極力避けたいはずです。
これまでのコラムでは、スムーズな債権回収のため、期限の利益喪失条項の重要性や、取引先会社が破産した場合の手続、公正証書のススメなどをご紹介しました。
今回は、債権回収の手段として利用される代物弁済契約について、概要から、実際に権利を実行するまでの手続、メリット・デメリットなどの注意点をご紹介します。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ 債権回収の鍵を握る「期限の利益喪失条項」~法的性質と実務上の活用 |
代物弁済とは
債務者が本来の債務(例:金銭の返還)を履行してくれない場合に、債権者と債務者の合意のもと、債務者の他の資産(例:不動産、動産、株式など)を給付することによって債務を消滅させる契約をいいます。平たく言うと、お金の代わりにモノで弁済してもうことです。
例えば、お金の貸し借りで考えると、お金を貸した人(債権者)は、借りた人(債務者)に対して、返還請求権という債権を有していることになります。債務者の立場から見ると、借りたお金を返さなければならない債務を負っていることになります。
この場合、本来なら債権者としてはお金で返してもらうのが原則であり通常の考えですが、債務者に返せるだけのお金(現金)がない場合は、いつまで経ってもお金(現金)で返してもらえません。しかし、債務者が不動産や動産、他者に対する債権といった現金以外の資産は有していることがあります。
そこで、債権者が「お金の代わりにその資産で弁済を受ける」と承諾し、その資産が債権者に引き渡されるなど所定の対抗要件が具備されれば債権債務は消滅するのです。これが代物弁済です。
代物弁済予約とは
将来、債務者が金銭債務を履行できなくなった場合に備えて、あらかじめ代物弁済をすることを約束しておく契約が「代物弁済予約」です。債権発生時にこの予約契約を締結し、担保の目的とします。
代物弁済の対象となる資産は、不動産、動産、株式、債権など多岐にわたります
抵当権との比較
不動産を担保とする代表的な手段である「抵当権」と代物弁済予約を比較すると、その特徴がより明確になります。
最も大きな違いは、権利の実行方法と所有権の帰属です。 代物弁済予約の場合、債権者は債務不履行時に「予約完結権」を行使し、法律に定められた清算手続きを経ることで、担保不動産の所有権を自ら取得して債権回収を図ります。 これに対して抵当権は、裁判所に申し立てて不動産を競売にかけ、その売却代金から配当を受けることによって債権を回収するのが原則です。抵当権を実行しても債権者自身が所有者になるわけではなく、競売で物件を落札した買受人が新たな所有者となります。
このように、債権者自身が所有権を取得できる点が代物弁済予約の大きな特徴と言えます。
一方で、残債務の扱いについては、両者に原則として違いはありません。 代物弁済予約で取得した不動産の評価額が債権額に満たない場合でも、別途その債務を免除する特約がない限り、残りの債務は存続し、引き続き請求することが可能です。これは、抵当権を実行したものの、競売の配当額が債権額に満たなかった場合に残債務を請求できることと同じです。
代物弁済予約契約締結から債権回収まで
代物弁済予約から債権回収(債務者の資産が債権者に移転する)までの流れは、次のようになります(ここでは主に、仮登記担保法が適用される不動産の場合を念頭に解説します)。
- 代物弁済予約契約の締結
- 権利保全のための登記・登録
- (債務不履行が発生した後)予約完結権の行使と清算通知
- 清算金の支払いと所有権の確定的な取得
代物弁済予約契約の締結
代物弁済の予約をするためには、債務者との間で代物弁済予約契約を締結しなければなりません。
一般的かつ簡単な代物弁済予約契約書に記載する項目と条項例は、次の通りです。
・【条項例:予約完結権】
「債権者は、債務者が本件債務の履行を怠ったときは、いつでも本予約完結の意思表示をすることができ、当該意思表示をもって代物弁済の効力が生じるものとする。ただし、対象財産が不動産の場合、仮登記担保法所定の清算手続を要するものとする。」
・【条項例:所有権移転登記(不動産の場合)】
「債務者は、仮登記担保法に基づく清算金の支払があったとき(または清算金がない旨の通知があったとき)は、直ちに当該不動産を債権者に引渡し、所有権移転の本登記手続を行わなければならない。登記費用は債務者の負担とする。」
権利保全のための登記・登録
契約を第三者に対抗(主張)できるようにするため、権利を保全する手続きが必要です。対象資産によって制度が異なります。
- 不動産の場合:所有権移転請求権の仮登記
不動産を管轄する法務局で「所有権移転請求権仮登記」を行います。これにより、後に第三者がその不動産を取得しても、債権者は自らの権利を優先させることができます。登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の10(1%)です。 - 動産・債権の場合:譲渡担保登記
動産や債権には「仮登記」という制度はありません。これらを対象とする場合は、通常「譲渡担保」という形式をとり、「動産譲渡登記」や「債権譲渡登記」を利用します。 これらは東京法務局(動産)や債務者の本店所在地を管轄する法務局(債権)で手続きを行います。登録免許税は1件あたり7,500円(または15,000円)です。
(債務不履行発生後)予約完結権の行使と清算通知
さて、契約を締結し、仮登記をした場合であっても、債務者がきちんと債務を履行してくれれば問題ないのですが、実際に債務不履行となった場合、債権者は「予約完結権」を行使します。これにより、直ちに所有権が移転するわけではなく、特に不動産の場合は法律で定められた清算手続きに入る必要があります。
債権者は、目的不動産の評価額を適正に見積もり、そこから債権額(元本、利息、損害金)を差し引いた金額(清算金)を計算し、その内容を「清算通知」として債務者に通知しなければなりません(仮登記担保法第2条)。この通知が債務者に到達してから2ヶ月間は「清算期間」となり、債務者はこの期間中であれば元本・利息・損害金を弁済して不動産を取り戻すことができます。
清算金の支払いと所有権の確定的な取得
清算期間が経過した後、不動産の評価額が債権額を上回る場合、債権者はその差額(清算金)を債務者に支払わなければなりません。この清算金の支払があって初めて、不動産の所有権が確定的に債権者に移転します(清算金がない場合は、その旨の通知をすることで足ります)。
清算金の支払義務と、債務者の不動産引渡・本登記手続義務は、同時履行の関係にあると解されています。 これで代物弁済による債権回収が完了します。
代物弁済予約契約のメリットとデメリット
債務者の資産で債権回収を図ることができるのであれば、代物弁済予約をしておいた方が何かと安心と思われるかもしれません。ただし、代物弁済予約に関しても、他の債権回収のための手段と同様に、メリットとデメリットがあります。
メリット
- 時価相当の弁済が期待できる
競売と異なり、市場価格に近い評価額での取得が期待できます。手続きも、当事者間の合意に基づき進められるため、競売に比べて迅速に進む可能性があります。
デメリット
- 余計な出費または満足的な債権回収にならないことも
代物弁済予約の対象物の査定額と自身が持つ債権額が対等額であれば、代物弁済予約の効力はとても大きいでしょう。
しかし、対象物の評価額が債権額を大幅に上回る場合、債権者は差額である清算金を現実に支払う必要があります。資金繰りの負担となる可能性があります。
査定額が債権額を下回る場合は、不動産所有権を取得することにはなるものの取得した資産だけでは債権全額を回収できないことになります。前述の通り、残債務は請求できますが、債務者に他に資産がなければ事実上回収不能となるリスクがあります。
- 費用と時間がかかる
先にご紹介した通り、仮登記には一定の費用がかかります。仮登記後の本登記の際にも、登録免許税がかかり、最終的にトータルで見ると費用倒れになるリスクもあります。
また債務不履行となった直後すぐに、所有権が移転できるわけではなく、最低でも2か月間の時間を要します。
最後に
債権未回収に備える代物弁済予約についてご紹介しました。代物弁済予約に基づいて債権回収をするためには、前提として、債務者に資産があることが必要となります。
もちろん代物弁済予約以外にも、債権回収を図る手続はいくつかあります。ケースバイケースで判断することになりますので、どれが正解というものがあるわけではありません。
債権回収でお悩みであればお早めに当事務所までご相談ください。事情等ヒアリングの下、適切な債権回収の方法についてアドバイス致します。