取引先が自己破産!債権者が知るべき『回収ルール』とやってはいけないこと
目次
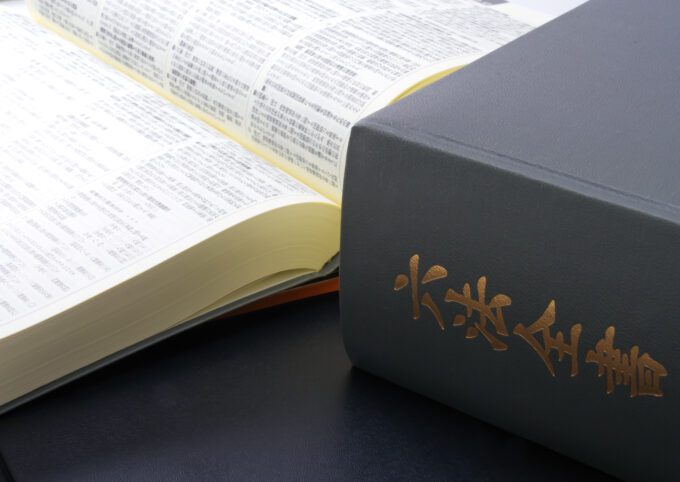
はじめに
債務者から債権を回収しようとする場合、通常は、まず債務者を訴え、勝訴判決(債務名義)を得る必要があります。その後、差押えなどの強制執行をして、初めて債権の回収をすることができます。
勝訴判決を得るまでの手続と、強制執行の手続は、全く別の手続きとなります。そのため、通常の流れで債権回収を図るには、この2段階を経なければなりません。
そして、債権回収においては、債権全額を回収できることは少なく、債務者の資力によっては、うまくいかないこと(回収不能)は実務上良く起こり得ます。
そのため、強制執行に入る前に、債務者の財産を可能な限り調査することが求められますが、調査を尽くしても、債務者の資力が乏しい場合、債務者が自己破産をしてしまう可能性は十分にあります。
そこで本記事では、取引先が「自己破産」を選択した場合、債権者としてどのように対応すべきか、その影響と注意点を解説します。
債務者に自己破産されるとどうなるか
自己破産とは、自己の収入等では債務を完済できない状況にある債務者が、裁判所の監督のもと、保有する財産を法律のルールに従って全債権者に公平に分配(配当)し、残りの債務について支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。
債務者が自己破産を申し立てると、裁判所から債権者宛に「破産手続開始通知」が届きます。この時点で、個別の取り立てや強制執行は一切できなくなり、債権回収は裁判所の手続きを通じて行われることになります。
必ず行うべき「破産債権の届出」
裁判所から破産手続開始の通知と同封されている破産債権の届出を、破産債権届出期間内に届け出なければ、その後の配当手続に参加することができなくなります。
債権の優先順位を知る|回収可能性の判断基準
債権の届出をしても、全額回収できることはまずありません。破産手続きでは、債権の種類によって支払いを受けられる優先順位が厳格に定められています。
破産者の財産から支払われる債権には、大きく分けて「財団債権」と「破産債権」の2種類があります。
1. 財団債権(最も優先される債権)
財団債権は、破産手続きによらず、破産者の財産から随時弁済される最も優先順位の高い債権です。
- 破産管財人の報酬
- 税金、社会保険料(納期限などによる)
- 破産手続開始前3ヶ月間の従業員の給料
- その他、手続きの共益費用など
2. 破産債権(財団債権を支払った後に配当される債権)
破産者の財産から財団債権が全て支払われた後、残りがあれば以下の優先順位で配当されます。
- (1) 優先的破産債権:財団債権に当たらない税金や従業員の給料など。
- (2) 一般の破産債権:友人からの借金や、取引先の買掛金、金融機関のローンなど、担保のないほとんどの債権はここに該当します。
- (3) 劣後的破産債権:破産手続開始後の利息や損害金など。
- (4) 約定劣後破産債権:契約であらかじめ他の債権より劣後すると定められた債権。
取引先に対する売掛金などの一般債権は、優先順位が低いため、財団債権や優先的破産債権を支払った後に財産が残っていなければ、配当は全く受けられないケースが大半です。
免責後の返済要求は法律で禁止されている(犯罪になる可能性も)
その後、債務者が免責許可決定を受ければ、返済義務がなくなります。免責許可決定が確定すると、返済義務は法律上消滅しますが、債務者が自ら任意で支払うことは差し支えありません。ここは、債権者・債務者ともに勘違いするところですが、免責許可後は、当該債務は自然債務(債務者が自ら進んで債務を弁済すれば有効であるが、債権者からは履行を法的に請求できない債務)となります。
つまり、免責となった後でも、債務者から任意で債権者に支払い、それを受け取ることは問題ありません。裏をかえせば、債権者側から支払いを請求・督促することは一切できません。
脅迫的な取り立ては厳禁です。
免責されたことを知りながら、債務者本人やその家族に対し、面会を強要したり、脅迫的な言動で支払いを要求したりする行為は法律で固く禁じられており、刑事罰(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金など)の対象となります(破産法275条)。
自己破産しそうな取引先への「駆け込み回収」は無効になる
「破産されたら回収できないなら、その前に無理にでも回収しよう」と考えるのは自然ですが、そのような行為は後に破産管財人によって「否認」され、回収した財産を取り戻されるリスクが非常に高いです。
- 強制執行や仮差押えの効力
訴訟を起こして勝訴し、破産申立て前に強制執行で回収したとしても、その時点で債務者が支払不能であったことを債権者が知っていた場合、その回収行為は破産管財人による否認の対象となります。また、破産手続が開始されると、それ以前に行われた仮差押えは効力を失います(破産法42条2項)。 - 特定の債権者への「偏頗弁済(へんぱべんさい)」
債務者が支払不能な状態にあることを知りながら、特定の債権者だけに優先的に返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます。強制執行によらず、話し合いで任意に支払いを受けた場合でも、この偏頗弁済に該当すれば、その弁済行為が否認され、受け取った金銭等を破産管財人に返還しなければなりません。 (※弁護士から「受任通知」が届いた後は、債務者が支払不能であると法的に推定されます。)
最後に
取引先が自己破産した場合、売掛金などの一般債権の回収は極めて困難になります。破産申立て前の駆け込み回収も、破産管財人の否認権によって無効とされる可能性が高く、法的なリスクを伴います。
残念ながら、多くのケースでは「泣き寝入り」に近い状態となるのが実情です。だからこそ、日頃から取引先の与信管理を徹底し、経営状況の悪化を早期に察知することが、債権者にとって最大の防御策と言えるでしょう。