なぜ利用されない?日本版司法取引の現状と、特殊詐欺への活用に向けた課題
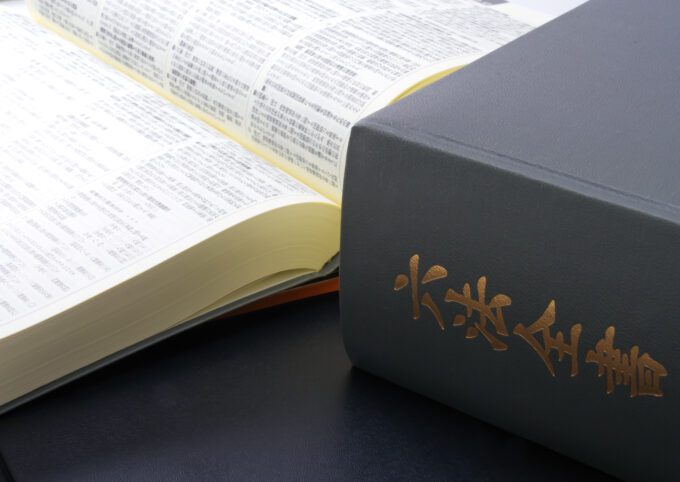
はじめに
2018年6月に導入された「日本版司法取引制度」。組織犯罪の全容解明の切り札として期待されましたが、運用開始から7年以上が経過した今、その適用事例は、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン氏の事件を含め、公表されている限りわずか6件に留まっています。
しかし最近、最高検察庁が特殊詐欺事件などへの積極活用を打ち出すなど、再び注目が集まっています。 本記事では、この日本版司法取引制度の仕組みと課題、そして今後の展望について解説します。
日本版司法取引とは?~アメリカとの違い~
日本版司法取引制度とは、被疑者・被告人が、他人の刑事事件について捜査協力(真実の供述など)をする見返りに、自身の事件で不起訴や求刑の軽減といった恩恵を受ける「捜査協力型」の制度です(刑事訴訟法の改正により、2018年6月1日から運用されています(刑事訴訟法350条の2~350条の15))。
「日本版」という名のとおり、そのモデルはアメリカにあります。
一般的に、司法取引には、自己負罪型と捜査協力型の2種類があり、アメリカの制度は前者、日本の制度は後者にあたります。
アメリカの司法取引モデルである自己負罪型は、自らの罪を認めることで刑罰を軽くしてもらう仕組みであり、イメージとしては「自首」が近いでしょう。
他方、日本における司法取引の仕組みとして採用されているのが、捜査協力型であり、あくまで組織犯罪などにおける他人の犯罪解明を目的としています。
制度導入の背景
近年、いわゆるトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)による犯罪が多発していますが、組織による犯罪は、以前から発生していました。その当時から、組織的な犯罪については、密行的に行われており客観証拠を集めるのが難しく、全容解明にあたっては被疑者らの取調べに依存しているところがありました。
しかし、トクリュウの出現により、以前にも増して被疑者らの供述を得ることが難しくなっていることや、供述を強引に得るために捜査機関による不当な取調べが行われることも社会問題化していきした。
そのような中、導入の決定打となったのは、2010年に発生した厚生労働省職員に対する大阪地検特捜部による証拠改ざん事件です。検事が証拠を改ざんするという前代未聞で、検察が社会的非難を受ける中、これまで過度に依存していた取調べの在り方を抜本的に見直すなどの刑事司法改革が行われた結果、2016年に刑事訴訟法が改正された際に、日本版司法取引制度が導入されました。
司法取引はの手続きの流れ
司法取引は、検察官と被疑者・被告人、そしてその弁護人の三者間で行われる「合意」です。大まかな流れは以下の通りです。
- 検察官からの提案:検察官が、被疑者側の持つ情報の重要性などを考慮し、「他人の犯罪について正直に話してくれれば、あなたの罪を軽くすることを検討します」と取引を持ちかけます(刑事訴訟法350条の2第1項)。
- 弁護人の同意が必須:被疑者・被告人が取引に応じたいと思っても、弁護人の同意が必須であり、これがなければ合意はできません。法律の専門家である弁護士のチェック機能が組み込まれています(刑事訴訟法350条の3第1項)。
- 三者による合意書の作成:検察官、被疑者・被告人、弁護人の三者が内容に合意すると、全員が署名した「合意書面」を作成します(刑事訴訟法350条の3第2項)。
- 協力の実行と見返りの提供:被疑者・被告人は、合意に基づき、捜査段階や法廷で真実の供述を行います(刑事訴訟法350条の2第1項1号)。その見返りとして、検察官は不起訴処分や、より軽い刑罰の求刑といった約束を実行します(同項2号)。
- 合意違反の場合:もし、被疑者・被告人が嘘の供述をしたり、偽の証拠を提出したりしたことが発覚した場合、この取引はすべて白紙に戻ります(刑事訴訟法350条の10)。さらに、嘘の供述などをしたこと自体が新たな犯罪(5年以下の拘禁刑)として処罰される可能性があります(刑事訴訟法350条の15第1項)。
対象となる犯罪
司法取引の対象は、主に財産犯や組織犯罪などに限定されています。
具体的には、死刑または無期拘禁刑に当たるものを除く一定の財産犯や薬物・銃器犯等とされており(刑事訴訟法350条の2第2項)、詐欺罪(刑法246条)、恐喝罪(刑法249条)、組織的詐欺・恐喝罪(組織的犯罪処罰法3条1項13号及び14号)、また、刑法以外にも租税法、独占禁止法、会社法、出資法、爆発物取締罰則、覚醒剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法、武器等製造法、銃砲刀剣類所持等取締法などに規定する犯罪も司法取引の対象となります。
公表されている適用事例は僅か6件
さて、司法取引が運用されてから7年が経過していますが、過去これまで司法取引が適用されている事例としては、公表されているものに限りますが、僅か6件です。
その多くが東京または大阪地検の特捜部によるもので、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン氏の一件も司法取引を適用した事例の一つです。このうち、警察の捜査段階で初めて適用された事件が2024年10月24日に神戸地裁でありました。
融資詐欺事件
自動車販売会社の元社長が、会社の預金や売上総利益を水増しした決算報告書を金融機関に提出し、金融機関から融資金4000万円を詐取したとして、決算報告書等の作成に関与した元社長、税理士、税理士法人職員らが詐欺罪などの容疑で逮捕されました。
この事件で、警察は、法人職員との間で司法取引を活用。これによって得られた証拠は、元社長に対する容疑の立証に生かされました。その後、元社長には懲役2年の実刑判決が下され、司法取引をした法人職員は不起訴処分(起訴猶予)となりました。
なぜ司法取引はほとんど使われていないのか?
鳴り物入りで導入されたにもかかわらず、なぜ利用がこれほど低調なのでしょうか。そこには、いくつかの理由が指摘されています。
- 検察官の抵抗感
日本の検察官の中では、「罪を犯した者と取引する」ことへの心理的な抵抗感や、安易な取引が冤罪を生むことへの警戒感が強いとされています。 - 被疑者・弁護人側の不信感
被疑者側から見れば、「正直に話しても、本当に約束通り軽い処分にしてくれるのか」という検察官への不信感があります。また、組織犯罪においては、仲間を売る「裏切り者」として、その後の身の危険を案じるケースも少なくありません。 - 虚偽供述による冤罪のリスク
これが制度の最大のリスクです。被疑者が、自身の刑を軽くしたいがために、無関係の第三者を巻き込む嘘の供述をする危険性が常に付きまといます。このリスクを恐れて、検察官も弁護人も取引に慎重にならざるを得ないのです。
特殊詐欺への活用と今後の展望
こうした課題がある一方、海外に拠点を置く特殊詐欺グループなど、従来の捜査手法では実態解明が困難な犯罪が増加しています。このような犯罪では、主犯の犯人はいわゆる飛ばしの携帯電話回線(他人名義や架空の人物名義で契約したもの)を使い実行犯に指示を行い、末端の実行犯(「かけ子」や「受け子」など)が仮に逮捕されても、彼らも主犯者とは会ったことがなくチャットや電話を通じて指示されただけの関係性というケースが非常に多く、なかなか首謀者にたどり着けない現実があります。つい先日も、カンボジアを拠点とする組織犯罪グループが逮捕されましたが、首謀者は明らかになっていません。
このような中、最高検は、2025年10月1日、日本版司法取引の活用が適切な事案では積極的に活用していくとして、司法取引を担当する検察官を新たに配置する方針を示しました。
なお、先ほどもお伝えした通り、過去に司法取引が適用された公表事例は僅か6件で、いずれも検察による捜査で行われたものです。警察の捜査段階で司法取引が活用されるのかは、先の融資詐欺事件以来、特殊詐欺事件では初となるか注目です。
司法取引制度では、被疑者又は被告人が虚偽の供述をしたなどの場合に罰則が設けられている(刑事訴訟法350条の15第1項)とはいえ、被疑者又は被告人からすれば、日本版司法取引は、自身の刑事事件で有利な処分を受けるための制度でもあるので(仮に司法取引によって不起訴となっても、検察審査会で起訴相当と判断されれば強制的に起訴される可能性はあります。)、虚偽の供述をもって、第三者が巻き込まれる可能性は完全に排除できません。
そのため、制度の活用を進める上では、虚偽供述による冤罪リスクに、より一層慎重に向き合う必要があります。供述の裏付けを徹底するなど、適正な運用が強く求められます。