【不動産シリーズ⑥】共有物分割請求訴訟
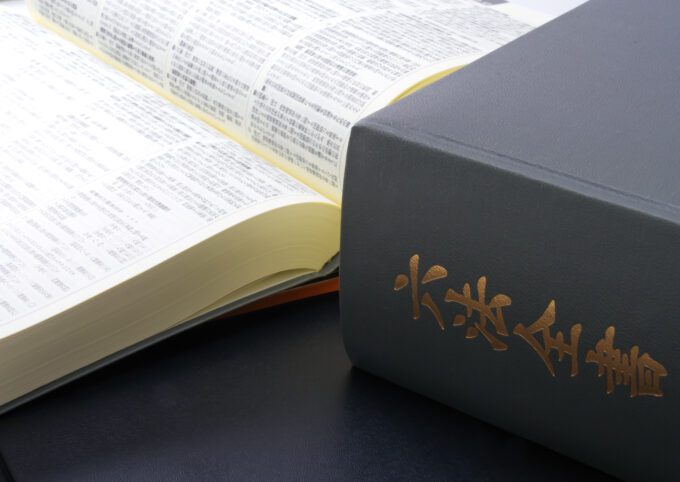
Q 親から相続した不動産を兄弟で共有しています。
しかし、私も兄もその不動産から離れて暮らしており、二人ともその不動産を管理しておらず、今後も住む予定がありません。
私は、早期に共有関係を解消して、不動産を売却したいと考えていますが、兄は親と一緒に住んでいた不動産だからなどと言って、売却に反対しています。
このような場合には私の持分を第三者への売却や放棄するほか、共有関係を解消する方法はないのでしょうか。
不動産の共有状態を解消する方法
まずは、話し合いによる解決
一般的に不動産の共有状態を解消するには、共有者間で持分の売買をする(代償分割)、不動産を共有者に持分に応じて分割する(現物分割)、共有者全員で売却をする(換価分割)、共有持分を第三者へ売却、共有持分を放棄する、という方法が考えられます。
これら方法のうち、代償分割、現物分割、換価分割を行う際には、他の共有者の同意が必要となりますが、他の方法に比べて、比較的解決手段としては合理的といえます。
いずれにしましても、まずは共有者間で話し合いをして不動産の共有状態の解消を目指します。 |
共有物分割請求訴訟による解決
共有者間での協議(話し合い)が調わないとき(協議不調)、またはそもそも協議をすることができないとき(協議不能)は、共有者は、その分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)。
つまり、裁判所に不動産の共有状態を解消する方法を判断してもらうということになります。
注意が必要なのは、薄々わかるかもしれませんが、共有物分割請求訴訟を提起する前に、共有者間で話し合いをすることが必須です。そのため、話し合いをせずにいきなり共有物分割請求訴訟を提起することはできません。
共有物分割請求訴訟の特徴
通常、訴訟と聞くと、平たく言えば勝ち負けをイメージするかと思いますが、共有物分割請求訴訟の場合は、その概念がありません。
つまり、Questionで兄が売却に反対しても、裁判所が原告(弟)の請求を棄却するということはありません。
次に紹介する分割方法のうち、裁判所が合理的または経済的であると判断した方法によって共有状態が解消されます。逆に言うと、共有物分割の請求した人が望んだ通りの解消方法になるとは限りません。 |
分割方法
代償分割
共有者の一人が、他の共有者に代償金を支払って、その不動産の全部を単独所有とする方法です。
代償分割が認められるためには、共有不動産を特定の者に取得させるのが相当であること、共有不動産の価格が適正に評価されていること、単独所有となる者に代償できるだけの資力があること、この方法で単独所有となったとしても共有者間の実質的な公平を害さないこと、が必要となります。
したがいまして、冒頭のQuestionで言うと、共有者である兄弟は今後も共有不動産を利活用する予定がないとのことなので、特定の者に取得させるのが相当とは認められにくく、代償分割は適切とはいえないでしょう。
現物分割
共有不動産を持分割合に応じて、物理的に分ける方法です。
現物分割が認められるためには、共有土地を物理的に分けることができること、それによって価格を著しく減少させないこと、が必要です。
→共有建物については物理的に分けるという話にはなりにくいでしょうし、共有土地を現物分割したとしても、用途地域によって何にもならなかったりするような場合は、認められにくいと思います。
→また現物分割の方法による場合、具体的にどう分割するのか、測量費用が発生する場合があります。
換価分割
共有不動産を第三者に売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。この売却方法については、裁判所による競売と共有者による任意売却の2つがあります。
一般的には、任意売却の方が競売よりも高く売却できることがほとんどなので、裁判官が競売という方法を考えているようなら、積極的に任意売却をしていくのがよいでしょう。
共有不動産の解消方法でお困りの方は弁護士にご相談を
不動産の共有状態を解消するためには、共有者間での話し合いで解決するのが効率的ですが、そうも言っていられない事情もあると思います。
そのような場合は当事務所までご相談ください。
具体的事情な事情や共有者間の反応などをヒアリングして、解決に向けたアドバイスを致します。