「不起訴処分」にも種類がある;「嫌疑なし」・「嫌疑不十分」・「起訴猶予」・「取下げ」・「罪とならず」
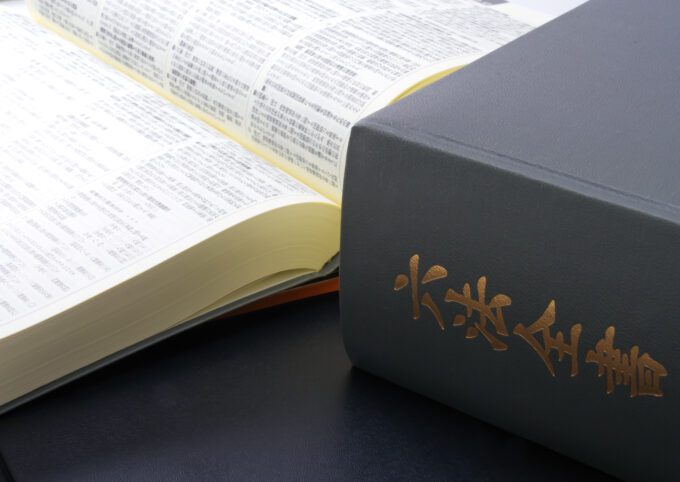
はじめに
不起訴処分とは、犯罪の嫌疑がかけられている人に対して、検察官が起訴しない処分をすることをいいます。加害者にとっては、一先ず安心する処分である一方で、被害者からすれば納得できない処分と思われる方もいるかもしれません。
ニュースなどでも、検察庁が「地検は●日、事件を不起訴処分とした。なお、検察は不起訴の理由を明らかにしていない。」とする報道を目にしたことのある方も多いかと存じますが、あれは検察庁が不当に被疑者を優遇して理由を隠匿しているわけではなく、被疑者および被害者の権利を保護するという理由があります(そもそも、処分理由開示をすべき法的義務は検察庁にはありません)。
今回は不起訴処分となる主な理由について、ご紹介したいと思います。
ちなみに、略式起訴が不起訴処分と思われている方がたまにいらっしゃいますが、略式起訴は、簡易な「起訴」手続をいいますので、不起訴処分ではありません。そのため、略式起訴となり、有罪となれば前科はつきますし、罰金などの刑罰を受けます。
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ 略式手続~略式起訴から略式命令まで~ |
不起訴処分の結果を受け取った告訴人は理由について請求できる
刑事告訴をした場合、捜査機関に捜査義務が発生しますが、刑事訴訟法上、捜査の結果、検察官は、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない(刑事訴訟法260条)とされています。そして、このうち、公訴を提起しない、つまり不起訴処分とした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければなりません(刑事訴訟法261条)。
不起訴処分の理由となる主な5つ
この点、法務省の事件事務規程(平成25年3月19日法務省刑総則第1号)では、不起訴裁定の主文に関する区分が規定されており、これがいわゆる不起訴処分の理由となります。
区分は全部で20あり、一部割愛しますが、実務上よく見られる主な理由を中心にご紹介します。
嫌疑なし
事件事務規程第75条2項17号は、被疑事実につき、「被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき」と規定しています。いわゆる冤罪や誤認逮捕などの事案がこれです。
つまり、ある人物を被告訴人として告訴し、その者を被疑者として警察が捜査したが、真犯人が別に見つかったことで、捜査対象となっていた被疑者が犯人でないことが明らかとなった場合や、捜査の結果、被疑者にアリバイがあった場合などは、嫌疑がないということになります。
嫌疑不十分
告訴を受け、捜査を開始し、罪を犯したという疑いが完全に晴れたわけではないものの、被疑者が犯人である証拠が不足している場合や、犯罪が成立するだけの証拠が不足している場合には、嫌疑不十分(証拠不十分)として不起訴処分になることがあります。
検察官は、起訴する際、有罪が勝ち取れるかを優先に考えます(これが有罪率99.9%の背景にある考えとも言えます。)。そのため、確実に有罪に持ち込める決定的な証拠がなければ証拠不十分として不起訴処分とするか、次に紹介する起訴猶予にする場合もあります。
イメージとしては、(勿論事案によりけりですが)、「この被疑者がこの犯罪を行ったのはまずそうなのだろうと思うが、公判で否認されたり被疑者の自白が取れていないなど証拠が足らない中では、無罪判決が出てしまうリスクがあるから、起訴は出来ない」というニュアンスです。
起訴猶予
嫌疑不十分とは言えない程の証拠はあり、起訴すれば有罪となる可能性が高い事件であっても、被疑者と被害者の間で示談が成立したというような状況では、起訴猶予となる可能性が高いです。
つまり、「犯罪の嫌疑はあるものの、検察の判断で起訴しない処分」、ということです。刑事訴訟法でも、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」としています(刑事訴訟法248条)。先ほどの示談の例以外にも、被害者の宥恕(許す)も犯罪後の情況になります。
ただし、起訴猶予を理由に不起訴処分となった場合でも、捜査機関の捜査を受けた事実はありますので前歴はつきます(前科はつきません。)。
また、あくまで猶予なので、時効が完成するまでは、後に新たな証拠が出てくるなどの事情がない限りは起訴されません。猶予期間は明示されるわけではなく、あくまで時効が完成するまでになります。この点は、執行猶予と勘違いしないようご注意ください。
取下げ
刑法などが規定する罪には、親告罪があります。親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪類型をいいます。
例えば、被害者が刑事告訴をした後、加害者との間で示談が成立し、告訴を取り下げた場合は、不起訴処分となります。
罪とならず
被疑者が犯罪者であったとしても、行為が刑法が規定する構成要件(犯罪成立要件)に該当しない、又は正当防衛(刑法36条1項)や正当業務行為(刑法35条)などの違法性なしとされる事由(違法性阻却事由)が証拠上明らかな場合は、罪とならずを理由に不起訴処分となります。罪とならずは、行為に着目した理由での不起訴処分です。
| 【参考条文】 事件事務規程(平成25年3月19日法務省刑総則第1号)第75条 不起訴の確定 |
| 1 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書により不起訴の確定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
2 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。 (1)被疑者の死亡 (略) (5)親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは請求をまって論ずべき罪につき、告訴、告発若しくは請求がなかったとき、無効であったとき又は取り消されたとき。 (16)罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。 (17)嫌疑なし 被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。 (18)嫌疑不十分 被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。 (略) (20)起訴猶予 被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。 |
| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
| ♦ 初めての刑事告訴:準備すべきことと手続きのコツ |
処分保留について
検察官が処分保留とすることがあります。
これは、刑事事件の手続上、検察官は身柄事件においては最長20日間の勾留期間内で必要な捜査を終え、最終的に起訴するか、不起訴にするかを決めなければなりません。
しかし、全ての事件が20日間で決められるわけではありません。必要な捜査はしたが、起訴するか、不起訴にするか更に追加捜査を行わねば決められないこともあります。その場合に採られるのが処分保留で、とりあえず被疑者を釈放します(というより、そのような状況では釈放するしかないのです。)。そして、検察官は処分保留にした後も、起訴するか、不起訴にするかを決めなければなりませんので、処分保留となった場合は、必ずどちらかの処分が下されます。
不起訴処分の理由のうち、起訴猶予が最多
2023年の検察統計によると、不起訴処分となった事件の総数は15万5305件でした。
このうち、起訴猶予が10万7272(約70%)、嫌疑不十分が3万2989(約20%)、嫌疑なしが2053(約1%)、罪とならずが2330(約2%)、取下げが6093(約4%。ただし、無効や請求の欠如も含む)、その他合計4568(約3%)でした。
以上の通り、示談成立その他事情、あるいは犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない(起訴猶予)と判断された割合が最も多く占めています。
このように、不起訴処分の理由として最も多いのが起訴猶予でした。やはり犯罪後の情況である示談の成立や被害者の宥恕文言、覚せい剤など被害者がいない事件であれば更生に向けた自発的な取り組み姿勢などが大きく影響すると思われます。